大学法人の損益分岐点について
2010年08月03日
大学法人の損益分岐点などというと違和感を覚える方々が多いかもしれない。なぜなら、大学法人とは営利追求を目的としない非営利法人であり、その非営利法人には期間損益の概念が存在しないからである。そもそも営利企業のために存在する損益という言葉そのものが学校法人に馴染まないとしてもそれは無理からぬことである。
にもかかわらず、損益分岐点分析の手法を大学法人の財務指標として活用しようとする根拠は何か。それは平成10年以降大学法人の帰属収支差額(=帰属収入-消費支出)がほぼ一貫して減少する中でコスト面からのより綿密・詳細な分析が重要になってきていると思われるからである。
下表は大学法人の損益分岐点関連指標を企業のそれに沿う形で示したものである(企業の売上高に当たるものを学校事業収入にするかそれとも帰属収入にするかによって指標が二通り考えられる)。
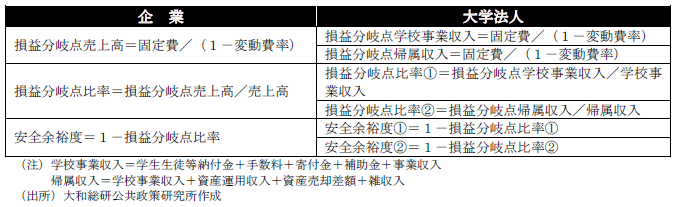
次に損益分岐点比率の算出の事例をみてみよう。
帰属収入1,000、消費支出900(固定費500、変動費 400)の場合
変動比率=400/1,000=0.4
損益分岐点帰属収入=500/1-0.4=833
損益分岐点比率=833/1,000=83.3%
ここで算出された83.3%が意味していることは、実際の帰属収入が833まで減少した場合、消費支出も833まで減少し、この時、帰属収支差額はゼロになるということである。
帰属収入1,000、消費支出900(固定費500、変動費 400)の場合
変動比率=400/1,000=0.4
損益分岐点帰属収入=500/1-0.4=833
損益分岐点比率=833/1,000=83.3%
ここで算出された83.3%が意味していることは、実際の帰属収入が833まで減少した場合、消費支出も833まで減少し、この時、帰属収支差額はゼロになるということである。
ところで、損益分岐点比率を算出するにあたって重要な作業が固変分解である。固変分解とは、総費用を固定費と変動費に分解することであり、その代表的な方法として勘定科目法と最小二乗法が挙げられる。勘定科目法とは、勘定科目ごとに固定費か変動費かを判断するものである。但し、固定費と変動費の完全な棲み分けができない場合は、適当な比率で按分するのもよいだろう。最小二乗法とは、回帰分析により、総収入Yと総費用Xの関係式を求めるものである。帰属収入をY、消費支出をXとしてY=aX+bという一次式が成立するためのパラメータ a、bを求める。ここでaが変動費率、bが固定費となる。どちらの方法を選択するかは随意だが、時系列データ数に限りがある場合は勘定科目法を選択せざるを得ないだろう。
18歳人口は今後8年間は120万人前後で推移するものの、その後は105万人~115万人前後に減少すると予想される。こうした将来環境の中で大学法人の帰属収入が今後減少する状況が生ずる可能性も否定できない。損益分岐点はこうした厳しい状況を想定し、現在のコスト構造の下で帰属収入が現行水準よりどの位減少するまで帰属収支差額がプラスを維持できるかをあらかじめ予測することができる。大学法人の財務の耐久力を把握しておく上で有用であろう。
ちなみに、大学法人(医歯系除く)の「損益分岐点比率(2)=損益分岐点帰属収入/帰属収入」は平成10年度以降悪化の傾向が続いている。
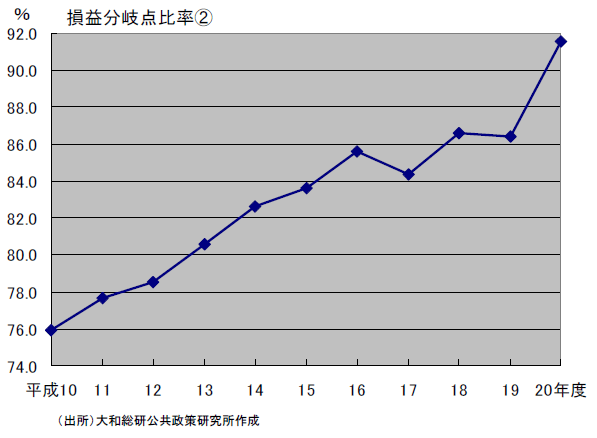
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
2026年1月鉱工業生産
普通乗用車などの大幅増産により自動車工業が生産全体を押し上げ
2026年02月27日
-
人手不足時代の外国人労働者の受け入れと共生の課題
潜在成長率を年率0.4%pt押し上げ/共生の鍵は日本語教育
2026年02月26日
-
テキスト分析が映し出す金融当局の楽観視
金融当局ネガティブ指数で、金融システムへの警戒感の変化を読む
2026年02月26日
-
ガバナンス・コードはスリム化するか?
原則の統合によって原則数減少、独立性判断方針の「策定・開示」から「策定」へ変更し要開示事項が減少
2026年02月26日
-
消費税減税より「最初の一歩」を。米国のトランプ口座が示す物価高対策
2026年02月27日





