事業利回りの低下、そうした時代の資金循環のあり方
2010年04月27日
次の図は総資本事業利益率、10年国債利回り水準および実質GDPの過去50年の推移を示したものである(※1)。3つとも低下傾向を辿っている。ターニングポイントは1973年ころであろうか。第一次オイルショックを機にそれまでの重厚長大型の日本経済が転換期を迎える年である。
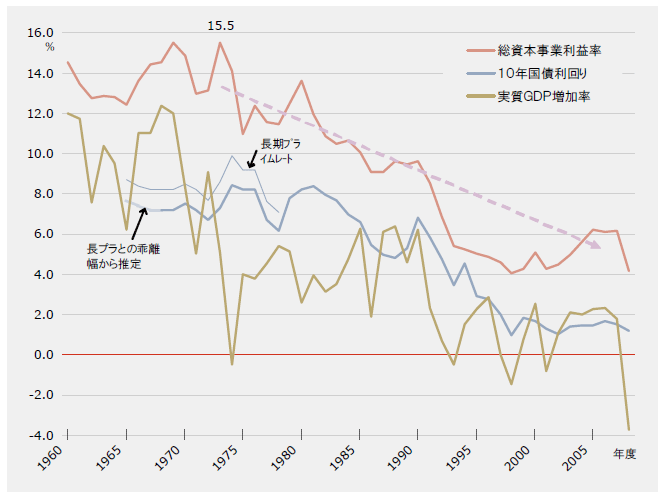
10年国債利回りと実質GDP増加率が互いに絡みつくような軌跡を辿るいっぽうで、総資本事業利益率は10年国債利回りの上方に若干の幅を保っている。「総資本事業利益率」はバランスシート上の総資産から現金預金と売掛・買掛資産を控除したものに対する利払前経常利益の比率であり、企業の事業投資利回りを表している。国債はリスクなしの投資とみなされるので、総資本事業利益率と10年国債利回りとの乖離幅は事業リスクのあるなしを示していると考えられる。金融機関の長期貸付利率は国債利回りと事業利益率の間にある。つまり、貸付利息の本質は企業が生み出す利潤の上澄みである。まとまった資金を10年国債利回りで仕入れ、企業に貸出し、事業利回りを獲得した企業から分け前をいただくというのが金融機関の運用側に属する収益構造である(※2)。
総資本事業利益率は、実質GDP増加率や長期金利に呼応するように低下傾向を辿っている。金利も下がっているので利払後ベースだとよく見えないが、本質的には事業利回りがだんだん低くなってきたということだ。同じ利益を稼ぐにしてもより多くの投資が必要になったとも言い換えられる。この傾向はバブル期に拍車がかかり、企業債務残高(※3)は95年度までの10年で2倍となった。その後過剰資産の圧縮期に入り約10年続いた。90年代後半を底に総資本事業利益率の軌跡が窪んでみえるのにはそうした背景がある。
グラフ上の総資本事業利益率は平均の概念であり、現実の世界はこれに近いところで中位集団が塊をなし上下に裾野を広げるように分布している。だから総資本事業利益率の平均が低下したといってもそれを上回るパフォーマンスをあげる企業は一定割合存在する。いっぽう、その後方の企業にとって平均、すなわち中位集団の水準が下がるということは、事業利益率が0%に近づく-場合によっては赤字転落する-蓋然性が高くなることを意味する。それに加えて不確実性も高くなる。設備投資、人件費その他固定費が損益の喫水線を上げ、利益水準が売上の変化に左右されやすくなるからだ。こうしたことが、企業において思い切った成長戦略を描けず、銀行も適当な貸出先が見出せない状況の背後にあるのではないか。
企業が積極投資を控えるいっぽう、それを埋めるかのように国や自治体その他の公的部門が、国債等で調達した資金を社会資本に「投資」してきた。90年代後半以降の公的部門は道路や公園のみならず、オフィスビルや百貨店も作っている。地方では野球場や劇場も手掛けている。利益を出すのが困難という属性から公共財の範囲が広くなり、日本経済における投資主体が企業から公的部門にシフトしているように見受けられる(※4)。これも「民業補完」のひとつだろうか。
重要なのは、すでに成熟した経済構造の下で平均的な事業利益率が下がっていることを認識し、それを前提とした財の最適配分の仕組みを考えることだ。企業活動においてはただでさえ低い事業利益率がさらに下ブレしないよう予測精度を高めるとともに支出のムダをなくすような種類の努力が求められる。相対的に役割が高まっている公的部門においては、持続可能性や最適配分の観点から市場規律の強化が期待される。現状を俯瞰すると、銀行が家計から資金を広く集荷し、国債を媒介として公的部門が社会資本等に「投資」するという構図がみえる。流通経路の複雑さゆえに家計の拠出した資金の行き先がよくわからなくなり、結果的に必要のないまたは収益性の乏しいところに投資されてしまうと困る。
この点では、たとえば、地域ファンドやレベニュー債(※5)のようなものを媒介として、地域住民の拠出と社会資本のつながりが明確になる仕組みが有効なのではないか。良い使い道にはお金がつき、そうでないものにはそれなりに。資金の流れを「見える化」することによってオーナーシップの向上とともにガバナンスの強化を図り、ひいては市場を通じた財政規律を利かせられるようになるからである。
(※1)図表の出所等
総資本事業利益率:法人企業統計(全産業)から次の算式で計算して求めた。
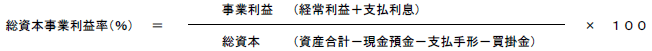
10年国債利回り、長期プライムレート:日本銀行および財務省
実質GDP増加率:国民経済計算
総資本事業利益率:法人企業統計(全産業)から次の算式で計算して求めた。
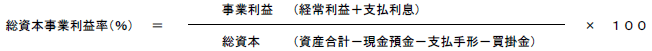
10年国債利回り、長期プライムレート:日本銀行および財務省
実質GDP増加率:国民経済計算
(※2)銀行などの金融機関は、家計等から広く預金をあつめて企業等に貸し出すことを業としているが、これは、預金を集荷して市場に卸すプロセスと、卸売市場から仕入れて企業等に貸し出すプロセスに分解して考えることができる。収益構造をみると、前者は、中値を下回るレートで調達して中値で運用するモデル、後者は、中値で調達し利ざやを乗せて企業等に貸し出すモデルである。これをビジネスモデルに敷衍して業態を定義すると、調達型(集荷型)のビジネスモデルと、運用型のそれに分類することができる。前者の極がいわゆる決済専業銀行であり、後者の典型がかつての長期信用銀行と考えられよう。なお、ここでいう「卸売市場」とは業者間(銀行間)市場であり中値を基準に取引される。10年もの国債流通利回りも中値を示すものとして機能する。
(※3)ここで企業債務残高とは法人企業統計(全産業)における「金融機関借入金(長期、短期)」と「社債」の合計をいう。
(※4)次を参照。「地方公営企業をみる3つの視点」(2009年4月22日付コンサルティングインサイト)「公益性のコスト」(2009年7月8日付コンサルティングインサイト)ただし、公営部門の「投資」が固定資産の形成という意味でどうかについて本稿では論点としていない。
(※5)「レベニュー債はなぜ実現しないのか」(2009年12月9日付コンサルティングインサイト)を参照。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

- 執筆者紹介
-
政策調査部
主任研究員 鈴木 文彦
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
2026年1月鉱工業生産
普通乗用車などの大幅増産により自動車工業が生産全体を押し上げ
2026年02月27日
-
人手不足時代の外国人労働者の受け入れと共生の課題
潜在成長率を年率0.4%pt押し上げ/共生の鍵は日本語教育
2026年02月26日
-
テキスト分析が映し出す金融当局の楽観視
金融当局ネガティブ指数で、金融システムへの警戒感の変化を読む
2026年02月26日
-
ガバナンス・コードはスリム化するか?
原則の統合によって原則数減少、独立性判断方針の「策定・開示」から「策定」へ変更し要開示事項が減少
2026年02月26日
-
消費税減税より「最初の一歩」を。米国のトランプ口座が示す物価高対策
2026年02月27日





