日本の国際競争力~為替市場が示すものは?
2010年04月21日
本年3月の為替市場は1ドル90.56円(月中平均)となり、17ヶ月連続で100円を切る円高となった。急激な円高が進んだ1995年でも8ヶ月連続(※1)であり、以降は一貫して100円を上回る水準で推移してきたから、今回の長期にわたる円高は異例と言える。円高は輸出産業の国際競争力を損なうから、景気への影響を懸念する声も聞かれる。
しかし、今の水準は本当に円高なのだろうか?前段の議論には2つの盲点がある。1つは米ドルと日本円の相場に限定していることだ。新興国の台頭が著しい今日、対米ドル・レートだけを見て為替市場を語ることの意義は乏しい。もう1つは物価変動の影響を考慮していない点だ。長引くデフレの中、物価上昇率がゼロ近辺で推移する日本に対し、大半の国で物価上昇率はプラスなのが通常だ。物価は各国企業のコストに影響するから、国際競争力を考える上で物価変動の影響は看過し難い。この2点をクリアしたのが、日本銀行が公表している実質実効為替レートだ。これは56カ国の通貨に対する為替レートを貿易額等に基づいて加重平均したものであり、物価変動の影響も織り込んでいる。実質実効為替レートで見ると、為替市場は全く違う様相になる。図はプラザ合意が行われた85年9月を100として実質実効為替レートの動きを示したものだが、これを見ると2000年以降は一貫して円安基調で推移しており、リーマン・ブラザーズが破綻した2008年9月直前の数ヶ月はプラザ合意当時以上の円安水準にあったことが分かる。直近ですらプラザ合意当時を16%上回る水準に過ぎない。現状の為替レートは円高ではなく、長く続いた円安が若干修正された程度、という理解の方が自然だろう。
懸念されるのは、このような円安が日本の競争力の低下を表している可能性だ。90年代後半以降、日本企業はほぼ一貫して資金余剰となっている。企業が投資よりもバブル期に積み上がった負債の返済を優先し、投資が長期にわたって抑制されたためだ。投資が競争力、ひいては経済成長の原動力となるのは経済学の教科書の教えるところであり、歴史が示すところでもある。投資の不足が競争力の低下につながった好例が英国だ。同国は世界各地に植民地を抱え、19世紀半ばまで繁栄を極めたが、1873年以降24年に及ぶ長い不況(大不況)を経験した。その背景には様々な要因が有ると考えられるが、その1つが国内投資の不足だ。繁栄の成果は大半が植民地を含む海外投資に充てられ、国内への投資は十分でなかった。その結果、軽工業から重工業への産業構造の変化への対応が遅れ、ドイツ・米国といった後発国に世界の工場の座を譲ることになった。今日、世界の工場と言えば中国を指すが、その経済発展にも海外からの直接投資が大きく寄与している。
活発な海外投資という点では今日の日本企業も同様だ。海外に子会社を設立する、或いは海外の会社を買収する日本企業は珍しくない。加えて、海外の子会社が稼いだ収益は現地で再投資され、国内に還流されないことが多い。2008年度の円高は、これらの子会社に対する持分(純投資)に関し約11兆円の為替差損をもたらした(※2)。同年度の名目実効為替レートは約12%の円高だから、単純に逆算すると日本企業の子会社に対する持分は90兆円に達する。国内よりも海外への投資が優先されてきた結果と言って差し支えないだろう。国内では高齢化、世界全体ではグローバリゼーションが進む中、海外への投資が増えることは悪いことではないが、国内投資の活性化無しに競争力向上は望み薄だ。国内投資を活性化させるような環境づくりが求められよう。
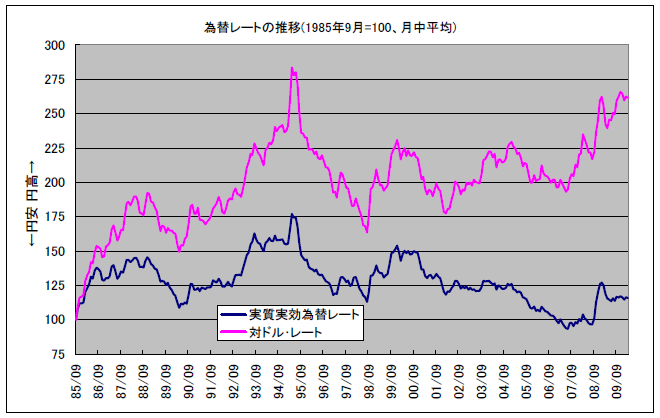
(※1)1994年12月(100.17円)を除くと94年7月-95年8月の13ヶ月。
(※2)会計上、為替換算調整額として処理される。損益計上されず、純資産を減少させる。また子会社には持分法適用会社を含む。
(※2)会計上、為替換算調整額として処理される。損益計上されず、純資産を減少させる。また子会社には持分法適用会社を含む。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
2026年1月鉱工業生産
普通乗用車などの大幅増産により自動車工業が生産全体を押し上げ
2026年02月27日
-
人手不足時代の外国人労働者の受け入れと共生の課題
潜在成長率を年率0.4%pt押し上げ/共生の鍵は日本語教育
2026年02月26日
-
テキスト分析が映し出す金融当局の楽観視
金融当局ネガティブ指数で、金融システムへの警戒感の変化を読む
2026年02月26日
-
ガバナンス・コードはスリム化するか?
原則の統合によって原則数減少、独立性判断方針の「策定・開示」から「策定」へ変更し要開示事項が減少
2026年02月26日
-
消費税減税より「最初の一歩」を。米国のトランプ口座が示す物価高対策
2026年02月27日





