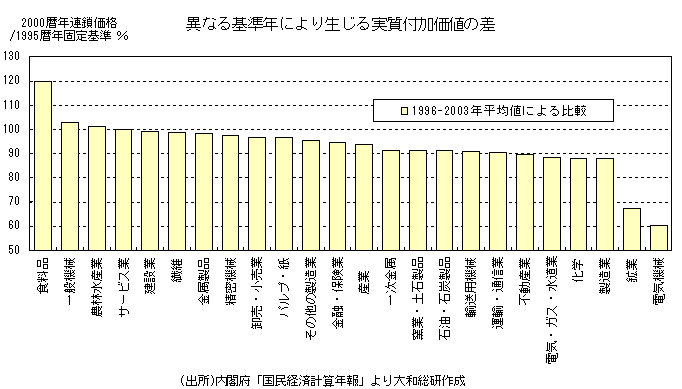労働生産性の盲点
2006年09月25日
| 日本経済は正常化し、過剰 設備の圧縮や金融不安は過去のテーマとなった。しかし、今後直面しうるのは労働生産性の向上というより重い課題である。OECD の統計によると、2004年時点で日本の労働生産性水準は先進国の中で最下位グループにあり、先進国トップのノルウェーの約5割強、米国の約7割、ユーロ 圏の約8割程度の水準にとどまっている。労働生産性の向上はあらゆる国にとって重要だが、人口減少社会を迎える日本では、その重要性は一段と高まるものと なる。 一国全体の労働生産性(労働投入(=就業者数×労働時間)一単位あたりの実質付加価値)の向上は、個別産業の労働生産性が高まるか、あるいは労働生 産性の高い産業の比重が高まることで達成される。 だが、この見方には盲点がある。下線部を労働生産性「上昇率」の高い産業と仮定すると、長期的にみて労働生産性上昇率が最も高い産業は技術革新のスピード が速い電気機械で、新統計(2000暦年連鎖価格)では、1996-2004年の労働生産性変化率が年率プラス12.6%と他の産業を圧倒している。次に 続くのは鉱業(年率プラス5.6%)、及び農林水産(同プラス4.7%)といった第一次産業で、以下は金融・保険(同プラス4.5%)、精密機械(同プラ ス3.5%)、運輸・通信(同プラス3.1%)となる。 このように、産業別の労働生産性変化率の比較は可能である。ところが、労働生産性上昇率の高い産業に労働力がシフトすることは、実は一般的ではない。労働 生産性上昇率の高い産業は、追加的な付加価値の生産に必要な労働力は、相対的に少なくて済むからである。1996-2004年の間で、労働生産性上昇率が 全体の平均以上の産業では、産業全体に占める労働投入のシェアは合計で2.6%低下している。旧統計(1995暦年固定基準)を用いて、1980年から比 較しても同様の傾向がみられる。 また、下線部を労働生産性の「水準」が高い産業と仮定すると、概念そのものが曖昧となる。名目付加価値は産業間での比較が可能だが、実質付加価値はデフ レーターの基準年が異なると変化するからである。一例を挙げると、1996-2003年平均の電気機械の実質付加価値は、新統計では旧統計と比べて約 40%も低くなる。これは、電気機械のデフレーターが恒常的に下落率が大きいことに起因しており、基準年を新しく(古く)するほど、実質付加価値は減少 (増加)する。 当然、この結果は労働生産性の水準にも影響を与える。まして、産業間の労働生産性水準の比較となると、より難しいものとなる。名目の労働生産性(=名目付 加価値/労働投入)を用いるのが次善の方法だが、労働生産性上昇率では他を圧倒する電気機械も、この値では産業全体をやや上回る程度である。最初に示した 労働生産性向上のメカニズムは不自然なものではないが、それ以前に必要なことは、労働生産性についての盲点を認識し、偏った先入観を払拭することである。
|
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。