2011年06月20日
東日本大震災により、日本の製造業のサプライチェーン(部品の供給網)が寸断され、企業の生命の危機に直面した企業の多くは、生産拠点を海外にさらに分散しようと検討している。もちろん、国内に踏みとどまって、再構築しようとしている企業も数多くある。海外移転先としてどこが候補になるのだろうか。中国が第一候補だろう。
日本企業の対外直接投資(FDI)にあって、一時の熱気は失せたものの、現在も中国への投資が続いている。対中投資は、2000年代前半の自動車を中心とした大型で沿海部への投資から、最近では、サービス業を中心に、投資規模が小さく、沿海部から次第に内陸地域への投資へと変化してきている。
現在の中国への投資ブームは第3回目のブームである。第1回目の対中ブームは、1980年代半ばに起きた。中国は1978年12月に体制改革・対外開放路線に踏み切り、積極的に外資企業を誘致した。深せん、珠海、アモイなどの経済特区をはじめ、上海、天津などの沿海地域14都市の対外開放を実施した。このときの日本企業の対中ビジネス戦略は、製品輸出が中心で、直接投資は少なく、欧米企業に比べ出遅れた。第2回目の中国ブームは90年代前半である。92年、当時の最高指導者トウ小平氏の南巡講話を契機に、中国は「経済成長加速・開放拡大」を推し進め、中国経済は高度成長期に入った。日本企業も積極姿勢を示し、中国からの輸出を目的とした「生産拠点」つくりが活発になった。
2000年から始まった今回の中国への投資ブームは、所得向上の著しい中国国内の市場をターゲットとしているのが特徴である。中国のWTO加盟(2001年12月)による規制緩和・市場開放への期待感と安定的な中国の経済成長が背景にある。「研究・開発」を日本で行ない、「生産」は中国で行なうというこれまでの日本企業の戦略が変わり、中国で「研究・開発」を行ない、中国市場から得られる開発課題に取り組むようになった。これが可能になったのは、中国国内の技術水準の高まり、優秀な技術者・人的資源の厚みが出来てきたこと、などの要因が指摘できる。
2000年代前半までは、広東省を中心とした華南地域では、内陸部からの出稼ぎ労働者は2-3年毎に交代し、その労働力は無尽蔵で、労働コストは上昇しないといわれた。しかし、状況は一変した。人民元の切り上げ、土地代の上昇、電力不足、外資優遇政策の見直しなど中国での事業リスクが台頭、中でも最大のリスクが人件費の大幅上昇になっている。中国政府は、社会不安の激化を怖れ、その最重点政策を、所得格差是正による「和諧社会」の実現においている。中央政府は、富裕層にマイナスになる相続税の導入、累進課税の最高税率の引き上げなど既得権益を侵すような政策を採りえず、最低賃金の引き上げが採りうる主な政策になる。昨年当たりから、労働者のストが多発、各地で最低賃金を20%超引き上げており、内陸部の諸都市でも大幅な賃上げが続いている。第12次5ヵ年計画(2011-15年)では、最低賃金を5年間で2倍にする計画(年間上昇率15%)である。
発展途上国は、通常、農村に過剰労働力があふれており、この安い労働力が絶えず工業部門に移ることで、高い経済成長を実現する(日本では1960年代に起きた現象)。農村における余剰労働人口が底をつくと労働需給が逼迫し、急速な賃金上昇が始まる。その転換点は「ルイスの転換点」と呼ばれる。中国ではその兆候が既に現れている。無尽蔵の安い労働力という中国の魅力が薄れ、労働コストの上昇は「世界の工場」の存立基盤を揺さぶっている。中国では2015年以降、労働人口(15-60歳)の減少が始まるとみられ(2013年から始まるとの見方もある)、2020年以降、労働人口の減少速度は加速する。
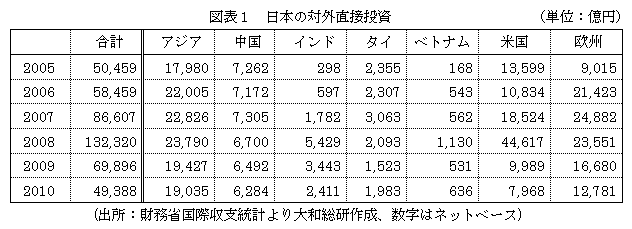
それでも中・長期の投資対象国として中国を有望視する日本企業は依然として多い。国際協力銀行(JBIC)が昨年12月に実施したアンケート調査でも09年に引き続き、中期的な有望事業展開先として中国をトップ(得票率77%)に挙げている。ちなみにインドが第2位で得票率は61%。中国を有望視する理由として、「現地市場の成長性(80%)」という要素を指摘する向きが圧倒的に多く、販売市場としての中国が最大の魅力と捉えている。中国での事業展開にあたっては、優位性を失った低コストを狙った労働集約型企業の進出に代わり、環境や省エネ・新エネルギーなどを軸とした技術集約型の企業には大きなチャンスがあろう。中国側の外資受入れニーズとも合致する。所得水準の急激な上昇により、高品質・高性能の日本製品を好んで受け入れる余地のある購買層も拡大し、新たな収益機会を提供することになるだろう。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
地域で影響を増す外国人の社会増減
コロナ禍後の地域の人口動態
2025年07月24日
-
コロナ禍を踏まえた人口動向
出生動向と若年女性人口の移動から見た地方圏人口の今後
2024年03月28日
-
アフターコロナ時代のライブ・エンターテインメント/スポーツ業界のビジネス動向(2)
ライブ・エンタメ/スポーツ業界のビジネス動向調査結果
2023年04月06日





