2012年08月29日
“日本再生戦略”における重点分野の1つに掲げられた医療が、成長産業であるということに疑問の余地はないだろう。一方で、同分野における公的支出拡大が、景気・雇用対策に有効であるにもかかわらず、拒否反応が強いのも確かであろう。その理由の1つとしてあげられるのが、個人レベルでは、給付と負担のバランスがとれていないことである。
一般の財・サービスでは、買手が売手に直接対価を支払うため、給付と負担は一致する。しかし医療では、買手である患者は対価のごく一部(※1)を負担するだけで、残りは第三者(税・保険料)が払うのが一般的である。そのため、患者以外の人にとっては、医療費の増加を「自分が払った保険料を他者が浪費している」と認識しがち(※2)である。
こうした人たちを納得させるには、医療費総額を抑制するか、自己負担率を高める必要がある。これまでの医療制度改革において、「医療費適正化」や「給付と負担のバランスをとる」ことが強調されているのも、同じ論理に基づいていると思われる。
給付と負担を完全に一致させるなら、一般の財・サービスと同様、患者が医療費全額を支払えばよい。しかしながら、自己負担が医療支出の主財源になっている先進国は皆無であり、財源に占める比率は平均で約19%(OECD加盟国)にとどまっている(残りは税か保険である)。
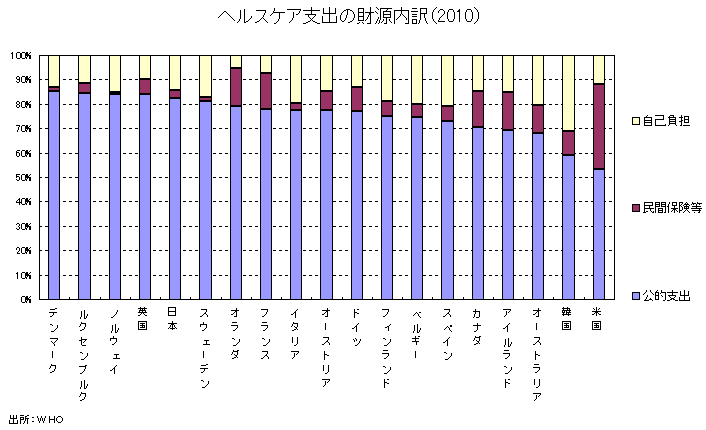
この理由は経済合理的なもので、「いつ病気や事故に遭遇するか」「いくら医療費がかかるのか」の予測が困難なことである。特に重症の場合には、巨額の治療費が必要となるだけでなく、働いて収入を得ることも困難になるためリスクが増大する。
ところが、多数の保険加入者でリスクをプールすれば、個々の加入者は低額の保険料負担でリスクを小さくすることが可能になる。国民のリスク回避性向が高いほど、患者負担の割合は下がり、保険支払いの比率が上がっていく。つまり、健常者が支払っている保険料とは、リスク回避の対価であり、「損をしている」のでも「他者に浪費されている」わけでもないのである。
もう1つの理由は価値観に基づくものである。個人レベルにおける給付と負担の一致とは、自分の病気は自分のお金で治すことを意味する。その場合、支払能力の低い人は受診できないケースも出てこよう。最悪の場合、死の転帰も免れない。正に、「人の命は金次第」である。
しかし先進国では、医療に関して平等の価値観が重視されており、多くの人々がこのような事態が起こることを望まないだろう。この価値観を実現し、国民の満足度を高めるためには、本人負担の割合は、できる限り低い方が望ましい。
第三者による支払いの大半が公的である理由も、この平等を重視する価値観によっている。リスク回避という目的達成のためだけなら、「民間にできるものは民間に任せる」ということで、民間保険を主体にすればよいだろう。しかし、民間保険では給付内容に応じて負担が異なってくる。給付内容の充実した保険に加入するには、高い保険料を払う必要があるし、既往歴のある人や高齢者は不十分な給付内容であっても、高い保険料を払わなければならない。最悪のケースでは、加入できないこともあり得よう。これでは本人負担と同様に、支払能力の低い人は病気を治せないことになってしまう。こうしたことから、ほとんどの先進国では、税や保険料といった公的支払いを医療支出の主財源にしているのである。
1961 年に国民皆保険制度が創設されたのも、「支払能力ではなく、万人が必要に応じて医療を受けられる」ことを実現するためであった。皆保険導入前の受療率を見ると、25~34 歳が最も高く、加齢とともに低下していたが、皆保険導入後にはその関係が逆転している。このことは、中高年と乳幼児(を連れて行く親)の相当数が経済的理由により、受診を断念していたことを示唆している。
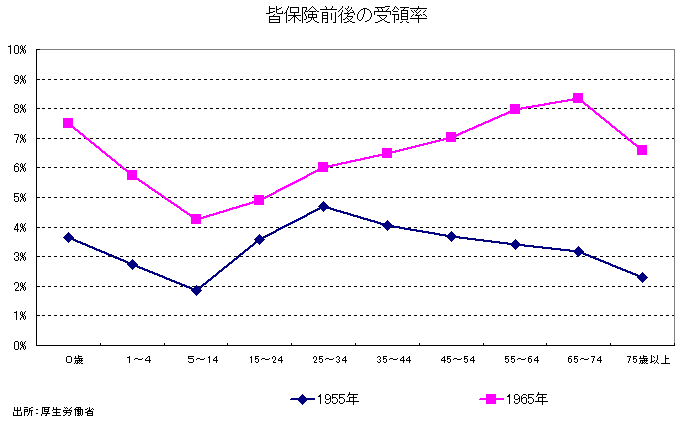
制度はいったん定着してしまうと、それ以前の状態や、目的・意義が忘れられがちだが、公的医療保険の存在理由は「人の命は金次第」でない社会を築くという、極めて重要なことなのである。
(※1)患者が医療機関で支払う自己負担額は、原則70歳以上が医療費の1割、70歳未満が3割だが、長期入院などにより医療費が高額になると、自己負担額が減額される“高額療養費制度”があるため、実際の自己負担率は15%程度になる。
(※2)75歳以上の高齢者が総医療費の約1/3を消費している一方、保険料と自己負担を合わせて1割しか負担していない“後期高齢者医療制度”が典型である。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
地域で影響を増す外国人の社会増減
コロナ禍後の地域の人口動態
2025年07月24日
-
コロナ禍を踏まえた人口動向
出生動向と若年女性人口の移動から見た地方圏人口の今後
2024年03月28日
-
アフターコロナ時代のライブ・エンターテインメント/スポーツ業界のビジネス動向(2)
ライブ・エンタメ/スポーツ業界のビジネス動向調査結果
2023年04月06日





