2012年03月14日
他社との経営統合や成長シナリオ策定等の経営戦略を検討するにあたり、戦略を実現するための組織基盤として持株会社化の必要性を併せて考える経営者も多いのではないだろうか。
では、実際に持株会社化を考える場合、何から考えればよいのか、移行スキームはどのように決定するのか、その際の検討ポイントは何か等様々な疑問がわいてくるものと思われる。ここでは、持株会社化を行う場合の移行スキーム選定の考え方を簡単に整理するとともに、検討ポイントを挙げてみたい。
持株会社化と移行スキームの関係
持株会社化を行う場合の移行スキームとしては、(1)共同株式移転、(2)株式交換、(3)会社分割、(4)単独株式移転の4つスキームの中から選択される場合が多いのではないかと思われる。(3)の会社分割に関しては、さらに、新規に設立した会社に対して会社分割を行う新設分割と、既存の会社や事前に設立した分割準備会社に対して会社分割を行う吸収分割の2つに分けられる。
次に、どのような場合にどのスキームを選択するかについてであるが、これは持株会社化の背景によって整理することできる。持株会社化の背景としては、細かく見ると各社毎に固有の事情があると思われるが、大きく区分すると他社との経営統合を直接の背景とした持株会社化と、会社単独での経営基盤強化を背景とした持株会社化の2つに整理できるのではないだろうか。
例えば、経営統合のため持株会社を設立し、その傘下に会社をぶら下げるような場合は、共同株式移転や株式交換、会社分割と株式交換の組み合せ等のスキームが選択される。また、会社単独で行う持株会社化の場合は、会社分割や単独株式移転が選択される場合が多いのではないだろうか。オーナー系の会社で親会社として資産管理会社が存在する会社が持株会社化する場合は、株式交換により資産管理会社を持株会社にするスキームが選択される場合もある。
過去行われた持株会社化の目的と選択された移行スキームの関係
参考までに、持株会社体制へ移行にあたり、どのようなスキームが選択されているかを過去10年ほど遡り調べてみた。対象は、2012年2月末時点で上場しており、2002年3月以降に会社分割や株式移転、株式交換等の組織再編等を行い持株会社体制に移行した上場会社とした。調査にあたっては、適時開示資料や有価証券報告書等の情報を参考にした。また、純粋持株会社であるか事業持株会社であるかは考慮しなかったが、持株会社体制に移行後、主要な子会社を合併し事業会社化した会社は除外した。
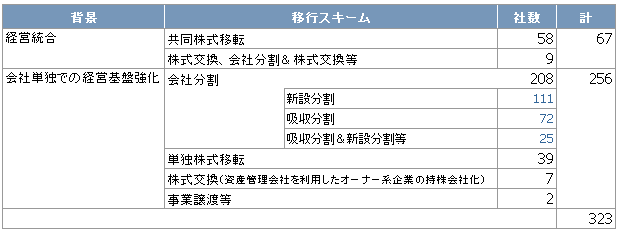
調査結果を見ると、経営統合を背景とした67社は、シナジー効果やコスト削減を目的として持株会社体制に移行したと思われるが、単独で持株会社体制に移行した会社が調査対象期間において256社もあることから、持株会社化が自社グループの事業戦略を効果的に推進するうえで重要な施策のひとつになっていると考えることができる。
実際の移行スキーム選定・実行にあたってのポイント
実際に移行スキームを選定するにあたっては、持株会社化の目的を踏まえ、税務面や法務・制度面、人事・労務面等からの多面的かつ慎重な検討が求められる。例えば、税務面では、土地建物等の資産をどの会社に保有させたいかを考え、資産の移転が必要になる場合は課税関係の影響を検討しなければならない。法務・制度面では、事業に必要な許認可等がある場合は、その取得に際し求められる条件や申請後許認可取得までに必要な日数等を考慮し、選択可能なスキームを検討しなければならない。
また、株式移転を選択するにあたっては、上場会社の場合、テクニカル上場申請等の手続も必要になるため、その対応工数や必要期間も考慮しなければならない。
このように、持株会社体制への移行プロジェクトは、それなりの準備と労力を要するものとなる。しかしながら、持株会社体制への移行自体は本来の目的ではなく、持株会社体制へ移行することで経営統合や経営基盤強化等を実現することが本来の目的のはずである。このため、持株会社体制への移行にあたっては、外部の専門家等を活用し、効率的に移行プロジェクトを進めていくとともに、貴重な人的経営資源は経営統合や経営基盤強化等の本来目的達成のために投入し、事業拡大や企業価値向上に向けた取り組みに注力することが持株会社体制への移行プロジェクトを失敗させないためのポイントとなる。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
持株会社体制の解消の意味を考える
近年の解消事例からグループ経営のあり方を見直す
2025年03月11日
-
経営統合のための持株会社化
~共同株式移転の事例から考える~
2025年02月14日
-
アフターコロナの企業戦略と持株会社化
~アフターコロナに持株会社化した企業の目的とは~
2024年07月12日





