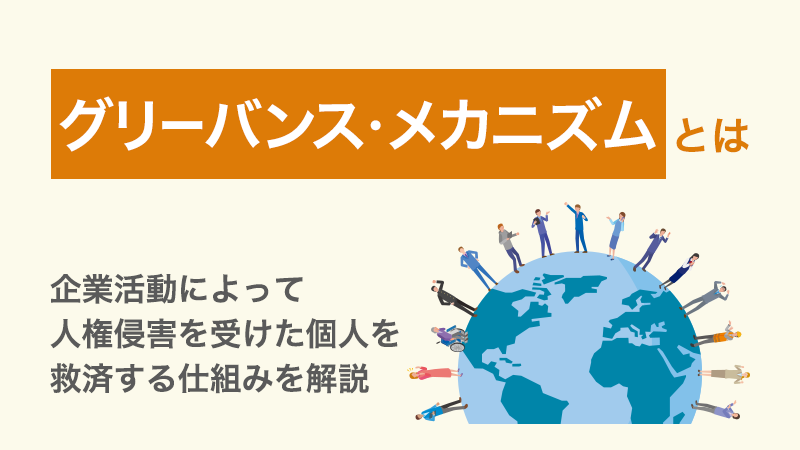
グリーバンス・メカニズムとは、企業活動によって人権侵害を受けた個人を救済する仕組みのことです。グリーバンス(grievance)は、不当な扱いに対する異議や苦情を意味し、苦情処理メカニズムと呼ばれることもあります。
2011年の国連人権理事会で承認され、企業による人権尊重の取り組みの指針となった「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護、尊重及び救済』枠組実施のために」(以下、「UNGPs」と表記)では、「人権を保護する国家の義務」、「人権を尊重する企業の責任」、「救済へのアクセス」の3つを「一般原則」と定めています(※1)。これらのうち、「救済へのアクセス」は国家と企業の両方に対応が求められます。企業に求められるのは「非司法的苦情処理メカニズム」の構築で、例えばハラスメントなどに関連した通報窓口が該当します。
欧米企業に比べて、日本企業の人権尊重への取り組みは全体として遅れていることが指摘されています。その一つがグリーバンス・メカニズムの構築です。どのように中小企業の対応を促すか、大きく広がったサプライチェーン上の問題に個社で取り組むことの限界をいかに乗り越えるかなどが課題として指摘されています。
このような中、日本企業の苦情処理を支援する取り組みが進展しています。2022年6月、一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(Japan Center for Engagement and Remedy on Business and Human Rights:JaCER)が設立されました(※2)。JaCERは、UNGPsに準拠して非司法的な苦情処理プラットフォームを構築し、会員企業(正会員のみ)の苦情処理を支援します。苦情処理メカニズムの正当性を担保し、苦情処理の実効性の向上を図ることを通じて、対話・救済の促進を目指しています。
もっとも、グリーバンス・メカニズムの実効性を確保する上で、「救済のブーケ(Bouquet of remedies)」という考え方が重要です。これは、ブーケが様々な種類の花から成るように、グリーバンス・メカニズムにも様々な種類のものが提供されるべきであるという考え方です。したがって、ある一つの包括的な仕組みがあれば十分というわけでもなく、ある個別の仕組みを「使われていない」というだけで実効性がないと判断することもできません。人権侵害を受けた個人が状況に応じてアクセスしやすいものを選べるよう、個社の取り組みも含め、複数の選択肢があることが望ましいと考えられます。
(※1)国際連合広報センターウェブサイト「ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合『保護、尊重及び救済』枠組実施のために(A/HRC/17/31)」(2011年 3月21日)を参照。この文書は、サステナビリティ日本フォーラムとアジア・太平洋人権情報センター(ヒューライツ大阪)が翻訳し、国連広報センターの「国連決議・翻訳校閲チーム」が校閲を行った。
(※2)一般社団法人ビジネスと人権対話救済機構(Japan Center for Engagement and Remedy on Business and Human Rights:JaCER)ウェブサイト(https://jacer-bhr.org/index.html)を参照。
レポート・コラム
2024年6月12日
人権尊重に関する企業評価と日本企業 2024年06月12日 | 大和総研 | 中 澪
2024年5月1日
人権尊重における機関投資家の役割 2024年05月01日 | 大和総研 | 中 澪
2024年2月14日
「ビジネスと人権」をめぐる日本企業の対応 2024年02月14日 | 大和総研 | 中 澪
2023年6月5日
LGBTQ+の人権をめぐる国連の活動の展開と日本企業への示唆 2023年06月05日 | 大和総研 | 中 澪




