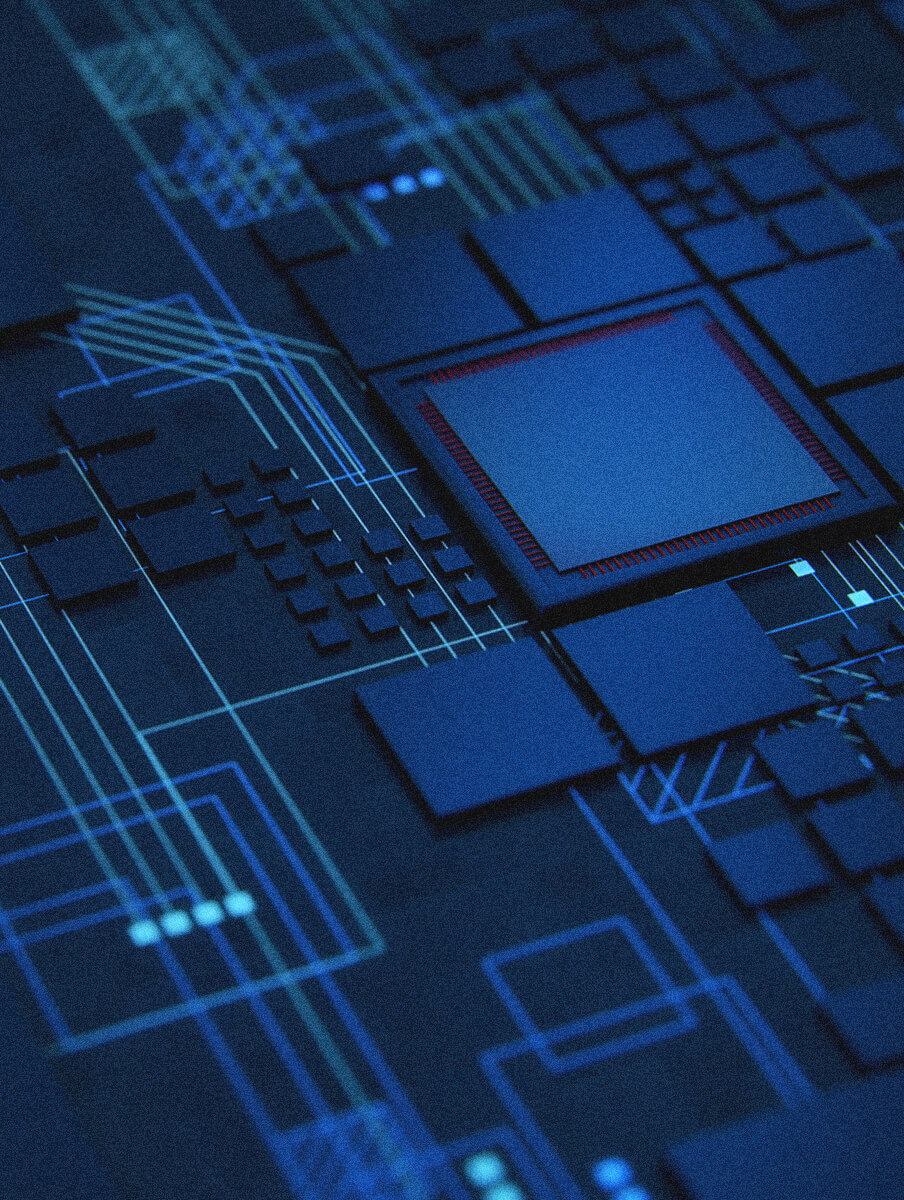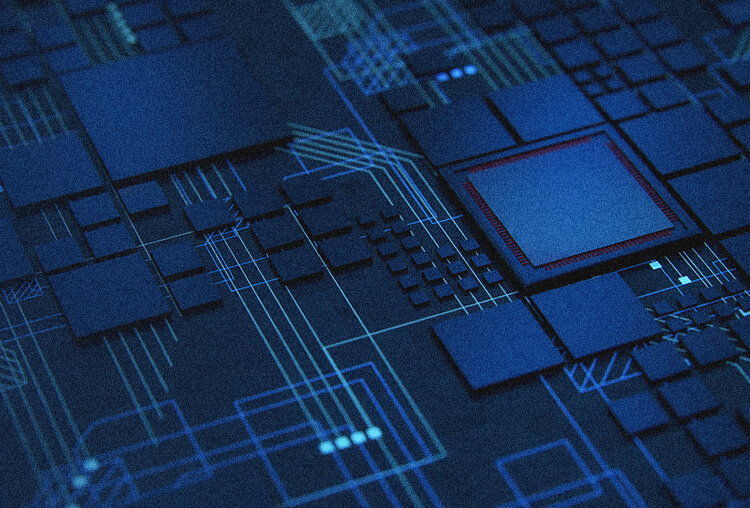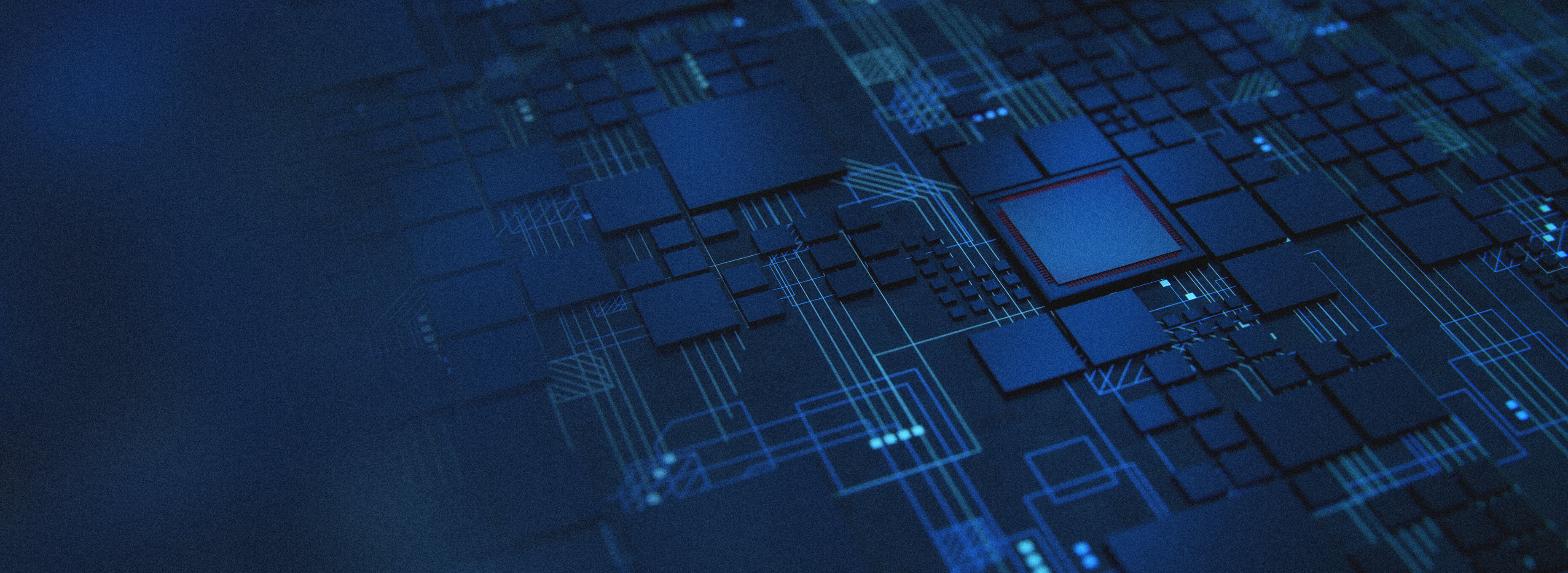格差の展開
2024年04月15日
日本は長きにわたる不況を脱したとの空気が漂い、物価といっしょに世間の給料も上がる見通しのようだ。その一方で、所得や資産の格差の方は、新しいNISAなど、なんとかしようという政策は発効したものの、縮まってはいない。家計だけではない。マスコミその他の論調では、企業社会でもGAFAMその他が世界を征服するのではないかと思うほどの勢いだ。
格差が拡大するのは今の日本や世界、あるいは政体に限ったものではない。復習すると、筆者の知る限りでも2000年近く前にはすでにあった。「持てる者は与えられていっそう豊かになり、持たざる者は持っているものまで奪われる」(意訳は筆者)という、おそらく多くの人が耳にしたことのあるフレーズは、マタイの福音書13章12節からの引用である。つまりイエスがこの世にいたころには、税金の取立人でさえ(あるいはだからこそ)格差は拡大するものだと認識していた(ということになっている)ということである。もうすこし卑近なところでいうと、ラッパーのバスタ・ライムスがマタイと同じことを言っている(‘Intro - There Is Only One Year Left’)。
格差とその趨勢的な変化を考えるとき、筆者がよくなぞらえるのは音楽とチューリップである。その昔、音楽は、絵画と同じく、貴族の邸宅内のものだった。それが音響技術の発達でライヴハウスやコンサート・ホール、そしてマイクとアンプ、PAシステムの発達でスタジアムや野外、つまり一般庶民の手の届くものになり、さらにインターネットと音楽配信サービスで各個人に同時配信されるまでになった。筆者にとってそれが何を意味するのかというと、消費する側から見ると音楽の価格は下がり、同時に、生産する側から見ると販売数量が増えてむしろ収益は大きくなっただろうということだ。おそらく王侯貴族に雇われていたときのほうがお客1人当たりの価格は高かっただろうが、稼ぎが大きいのはコンサート・ホールで演奏するようになってからだろう。
同じような仕組みが投資業界の歴史に残るチューリップ・バブルにも見られる。珍しい色の花をつけるチューリップの球根1個当たりの値段はバブル時に家1軒にも相当したとのことだが、値段が高いがゆえに研究開発が進み、その色の球根の作り方が解明されると生産量が増え、珍しくなくなって値段は暴落した。それでも、そんなチューリップの生産者の利益はおそらく値段が下がった後の方が大きかった。
そうやって消費者側は民主化がなされたわけだが、生産者側はどうだろう?
インターネット、あるいは動画配信サービスが広まった初期、これで誰もが情報の発信側になれる、インフラという参入障壁は消えたも同然、どんなマニアなニーズにももれなく応えられる供給者が現れる、究極のニッチな市場群が実現するのではないか、そんな予測もあった。しかし現実はどうかというと、一握りの供給者/配信者に需要が集まり、中間層は稼げなくなった。昔でいえば、町ごとにいた流しの演奏者は、以前なら王侯貴族の前でだけ演奏していた人たちの音を録音した音源に取って代わられた。近年でいえば、音楽配信サービスの普及で顕著になったのは、市場の細分化ではなく一握りの曲やミュージシャンが売り上げの大部分を占める、べき乗則に従う市場だった。「そこそこ」では食えなくなったのである。
さて、このように、誰もがいいものに手が届く環境では、消費者はいい思いができるが、生産者は一握りのトップ・クラスに入らないと仕事がなくなる。加えていうと、トップ・クラスの人たちは地位が確立されているので、AIや機械に(そんなものが判定可能だとして)同じ品質の製品・サービスが提供可能だとしても、消費者はトップ・クラスの「人」にそれを提供してもらうほうを好む。しばらく前、コマーシャルの登場人物にAIタレントが起用されたが、だからといって「CM女王」のレベルの人をAIタレントで置き換えるのは、二次元好き向けを除けば、たぶん無理だ。
消費者の多くは生産者でもあるので、定義によって(誰もがトップ・クラスというのはレイク・ウォビゴン以外では実現しないようだから)大部分の人は「食えなくなる」。歴史上、そんな展開と状況を食い止めたり覆したりしてきたのは革命や内戦なのだろうが、近年なら……スキャンダルとすっぱ抜きだろうか。どれもあまり幸せな道ではないので、ベーシック・インカムでもお金のかからない幸せでも、何かもっと穏便な解決策が開発されることを望む。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。