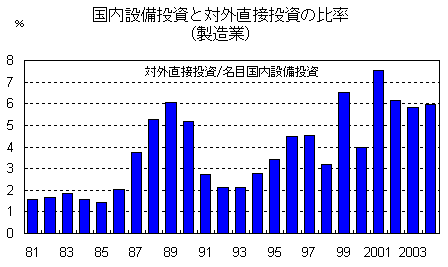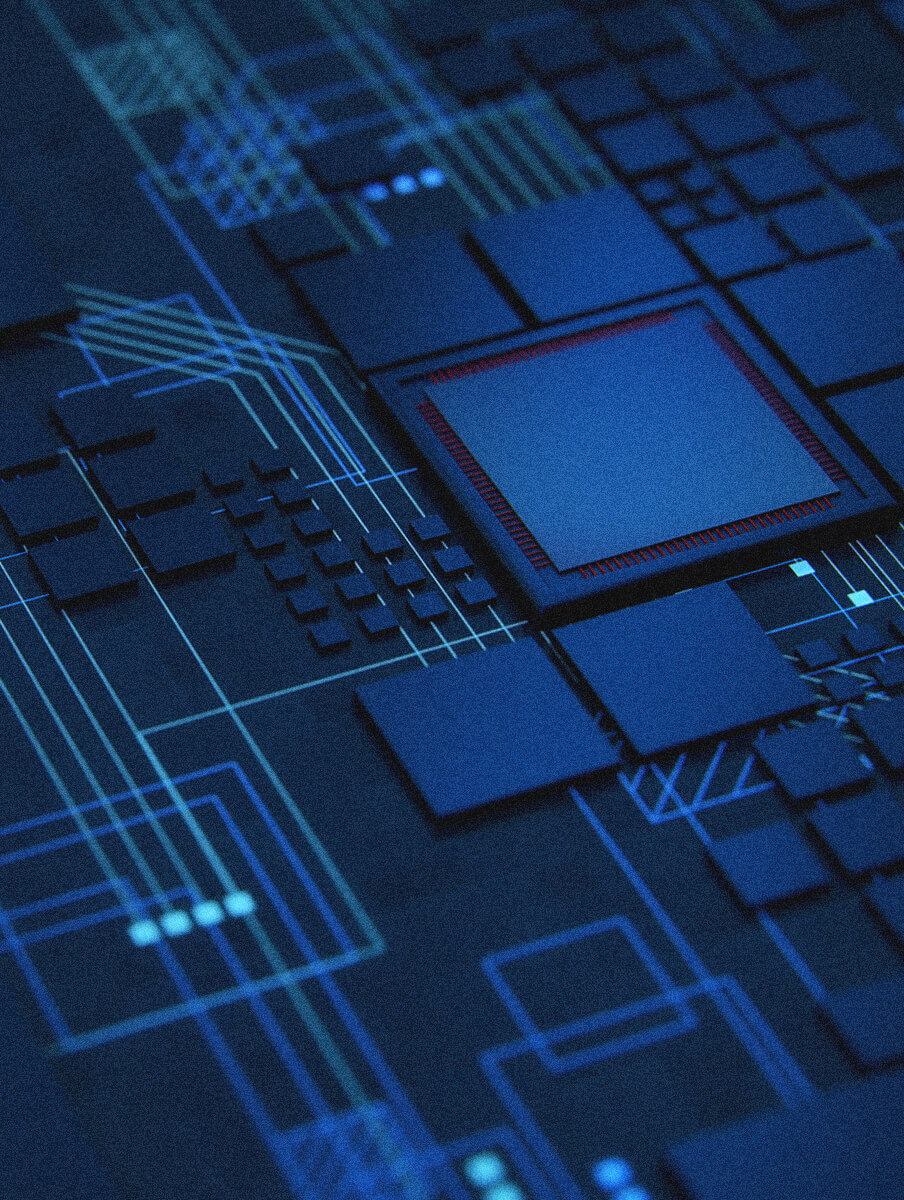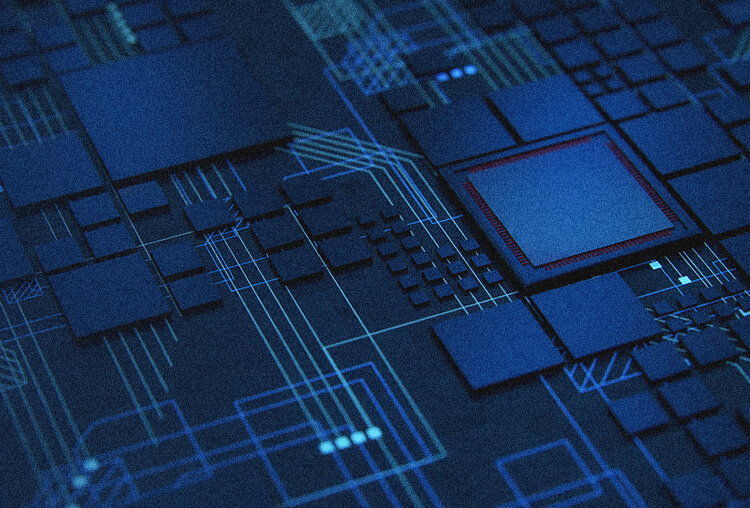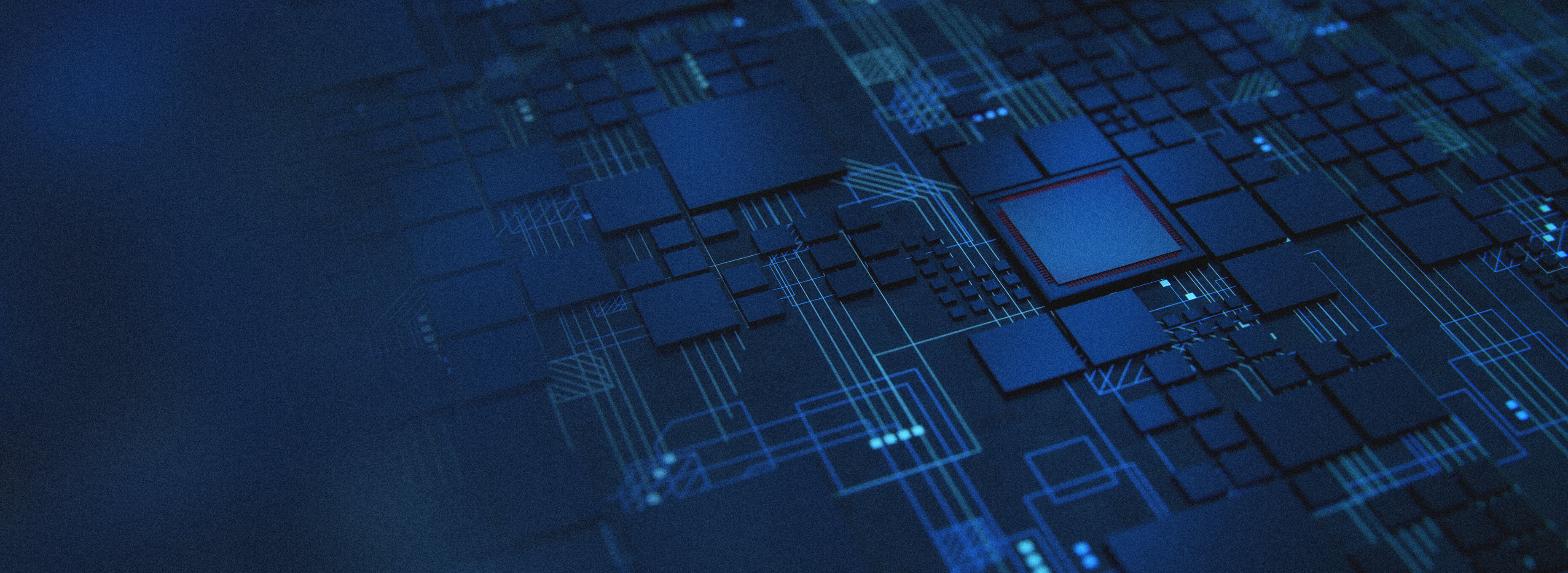投資の「国内回帰」?
2005年09月07日
注目を浴びるテーマは、時として実情以上の印象を与えることがある。例えば、英米は大陸欧州よりも経済状況が良好で、かつ経済効率や労働生産性で優位に立つといったイメージを抱きやすい。OECDによると、米国の時間当たり労働生産性は1995年—2004年まで年率2.4%の上昇、英国は同期間で2.3%上昇しており、大陸西欧地域でこれ以上であるのはギリシャ(3.0%上昇)、スウェーデン(2.4%上昇)、フィンランド(2.3%上昇)に限られる。ところが、時間当たり労働生産性の絶対水準をOECDのデータで比較すると、米国を100として、2004年時点でノルウェー(125)、ルクセンブルグ(124)、ベルギー(113)、フランス(107)、アイルランド(104)、及びオランダ(100)が米国と同等以上である。また、オーストリア、デンマーク、ドイツ、イタリアも90以上で、いずれも英国(87)の水準を上回っている。このように、1990年代後半以降の英米は、労働生産性の「上昇率」が相対的に高かっただけであり、労働生産性の水準で他国を引き離しているわけではない。
(出所)内閣府、財務省、日本銀行の統計より大和総研作成 (注)年度単位。対外直接投資は国際収支(財務省、日本銀行)の総額を、対外及び対内直接投資状況(財務省)における製造業の比率で按分、名目国内設備投資は、GDPベース(内閣府)の総額を、法人企業統計(財務省)における製造業の比率で按分した。 |
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。