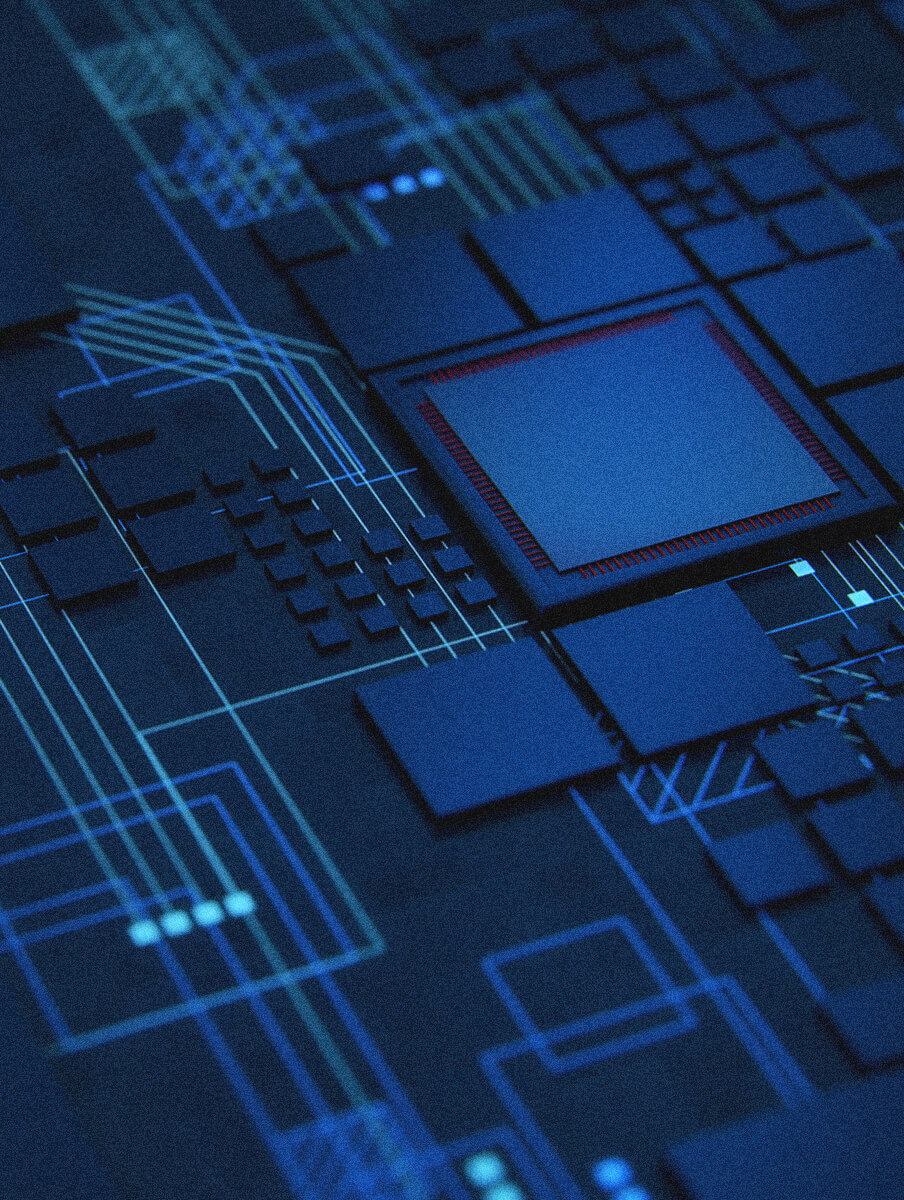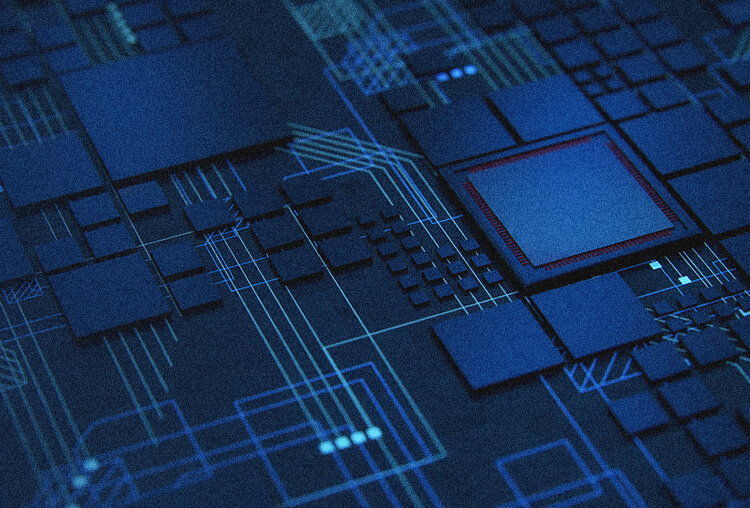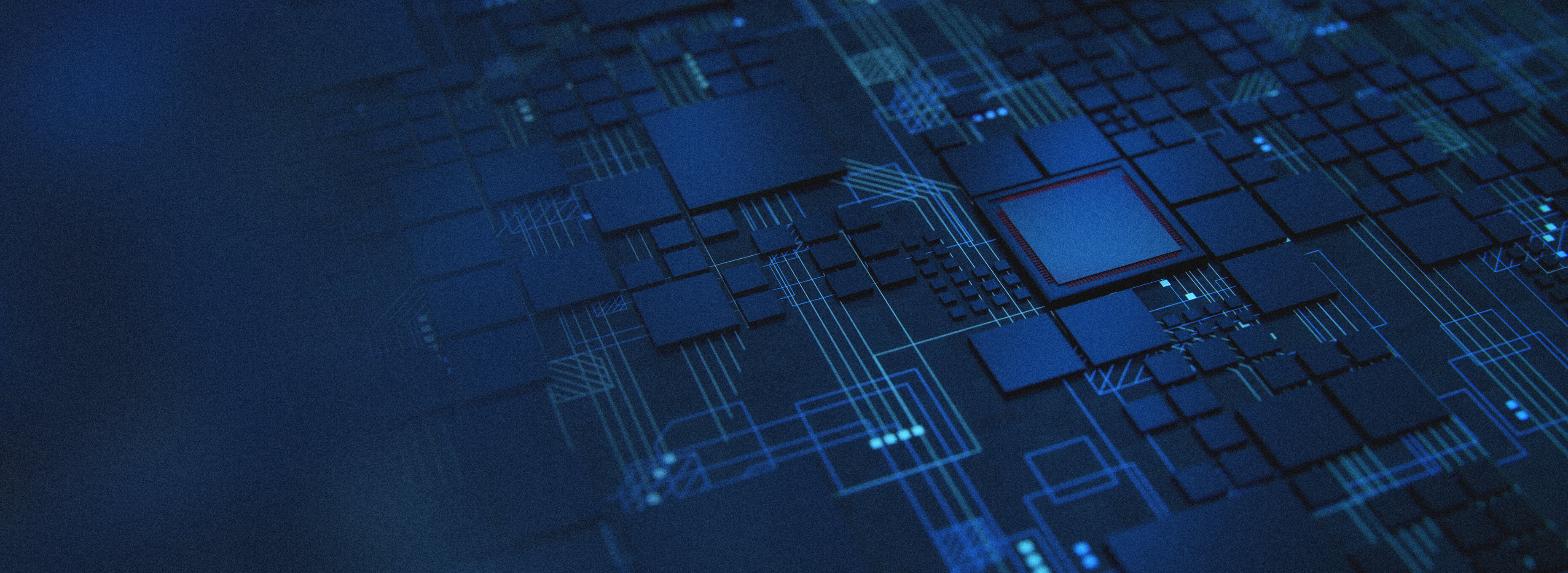2012年09月19日
1.退職給付会計が原則主義へ
退職給付会計基準が2012年5月17日に改正された。公開草案が2010年3月に公表されていたので、2年越しの決着ということになる。新しい退職給付会計基準では、PBOの計算手法及び会計処理ともに、IFRSにおける退職給付会計基準であるところのIAS第19号におおむねコンバージェンスした内容となっている。
今回の基準確定を受けて、各企業はPBO計算の前提となる「割引率」や「退職給付見込額の期間帰属方法」の選択について、本格的な検討をスタートさせつつある。この検討開始段階において、新たな課題となっているのは、原則主義に基づく会計基準であるとされるIFRSへのコンバージェンスに伴い、企業が各社の実態に応じて主体的かつ合理的に計算の前提を選択していく必要性が生じている点である。
従前の退職給付会計基準は、実態としては細則主義の側面が強く、「割引率」の水準だけ企業が指示すれば、半自動的にPBOが算出(※1)された。また、「割引率」自体も水準のみの指示であり、PBOの計算手法に立ち返って、その設定方法を選択するということはなかった。
これに対して、新退職給付会計基準では、「割引率」及び「退職給付見込額の期間帰属方法」の2点に関して、PBOの計算手法に立ち返ってその設定方法を選択することになっている。
2.2つの期間帰属方法
本レポートでは、退職給付会計コンサルティングを進めていく中で、特に多くの検討時間を要することとなる後者の「退職給付見込額の期間帰属方法」について、そのポイントを解説したい。
まず初めに、PBOが算出されるまでの一連の流れを確認する。PBO計算では、「退職給付見込額」として予定昇給率や予定退職率を使用して将来の退職給付額を見積もる。その「退職給付見込額」のうち、決算時点までに積み立てておかなければならない金額を算定し、当該金額を適正な金利により割り引いてPBOを算出する。この一連の流れの中で、「退職給付見込額」のうち、決算時点までの要積立額を配分するプロセスを「退職給付見込額の期間帰属」という。
新退職給付会計基準では、「期間定額基準」と「給付算定式基準」という2つの期間帰属方法が設定されているが、その比較イメージをまとめると以下のとおりである。
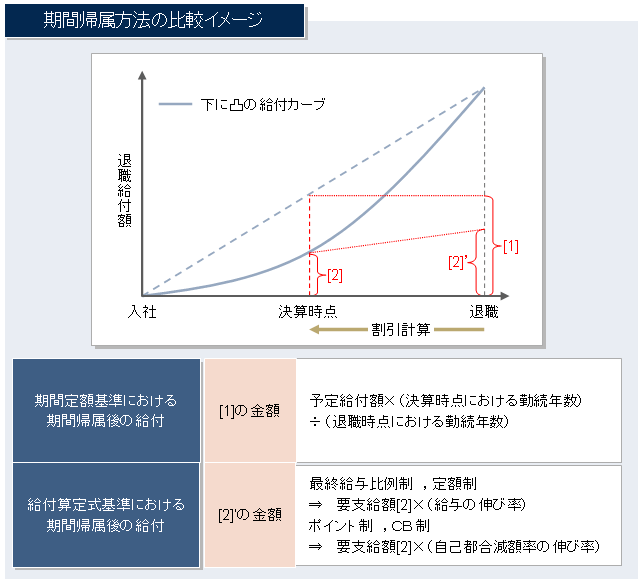
ここで、2つの期間帰属方法の特徴を概観する。まず、「期間定額基準」であるが、この期間帰属方法は従来の退職給付会計基準では原則的な取り扱いとなっていた。「期間定額基準」は、給付設計にかかわらず、決算時点までの発生分を勤続年数比により配分するので、シンプルで理解し易い期間帰属方法といえる。IAS第19号には「期間定額基準」という選択肢は存在しないが、「期間定額基準」を一律に否定する根拠がないことや、適用の明確さでより優れていることから我が国の新退職給付会計基準では選択肢の一つとして残された。
もう一方の選択肢である「給付算定式基準」は、IAS第19号で認められている期間帰属方法である。その1つ目の特徴は、上図のイメージグラフのように「給付カーブが下に凸(※2)」の場合、「期間定額基準」に比べてPBOが少額となる傾向のあることである。このことは、図中の[2]’の金額が、[1]の金額を下回っていることから理解できる。
そして、2つ目の特徴は、1つ目の特徴と表裏の関係にあるが、給付が著しく後加重となるケースでは均等補正が必要となることである。ここで、均等補正とは、給付が著しく後加重となるケースにおいて、過度な費用の先送りを避けるため、その間の給付が均等に生じるとみなして補正した給付算定式に従ってPBOを見積もることである。
3.「期間定額基準」を採用する場合の検討課題
2つの期間帰属方法には以上のような特徴があるが、実際にコンサルティングを開始する場合にまず問題となるのは、今回の会計基準改正時に引き続き「期間定額基準」を採用する場合の今後の対応である。新退職給付会計基準第82項には、「・・・適用初年度後において、正当な理由により退職給付見込額の期間帰属方法を変更する場合には、原則として、企業会計基準第24号第6項(2)の定めに従って遡及適用することになる。」とある。企業会計基準第24号第6項(2)は、「会計基準等の改正によらないが、正当な理由により会計方針の変更を行う場合」の遡及適用について、その取扱いを定めている。この条項には、新会計方針は「過去の期間のすべてに遡及適用する。」と規定されている。このため、例えば3月末決算の企業(※3)が2014年4月に引き続き「期間定額基準」を採用するケースで、その後、何らかの正当な理由により、「給付算定式基準」に変更する場合には、2014年4月から「給付算定式基準」に変更する年度までの全ての期間について、遡及して「給付算定式基準」によるPBOを算出しなければならない。
ここで、この全過去期間への遡及とIFRS適用の関係について考えてみる。IFRSの適用については、2012年7月2日に企業会計審議会から「中間的論点整理」が公表されており、その中でIFRSの適用範囲や適用時期については引き続き審議を継続する旨、適用方法については連単分離の許容が現実的である旨、記載されている。このような状況を踏まえると、何年か先に連結決算にのみIFRSが適用されるような仕組みが整えられ、その対象に自社が含まれている事態も想定される。こうしたケースで、2014年4月に引き続き「期間定額基準」を採用していた場合、単体決算では「期間定額基準」、連結決算では「給付算定式基準」でPBOを算出しなければならなくなる。そして、その不都合を解消すべく、単体決算におけるPBO計算を「給付算定式基準」に変更しようとすれば、2014年4月まで遡及適用しなければならない。IFRSの適用時期が後ろに延びれば延びる程、遡及期間が長くなる。遡及期間が長くなれば、従業員データ、給付設計を変更しているケースではその履歴等、計算前提の確保に支障をきたす可能性がある。また、新たな計算委託料が発生する等、費用面でも負担が増加する。連結決算にIFRSが適用される場合には、IFRSの初度適用(IFRS第1号に規定)に伴い、報告期間の前期期首まで遡り「IFRS開始財政状態計算書」を作成しなければならないが、この初度適用とは別に、今回の会計方針の変更は、全ての過去期間に遡及適用しなければならない点に注意が必要である。以上が、コンサルティング開始時にまず初めに直面する課題である。
4.「給付算定式基準」を採用する場合の検討課題
更にコンサルティングを進めて行き、「給付算定式基準」への切り替えを検討する場合にも、課題はある。給付カーブの形状によっては、「期間定額基準」を採用する場合よりもPBOが減額となる傾向があり、そうした場合の一定の歯止めとして、「均等補正」が必要となる点は先程触れているが、この「均等補正」が難題となる。まず、「均等補正」の必要性の判断であるが、新退職給付会計基準の適用指針第75項には「考え方を特定することにより、かえって国際的な会計基準との整合性が図れないおそれがある」ため、具体的な考え方を示さないとなっている。従って、「均等補正」の必要性は、個別事例毎に判断しなければならない。このため、企業は、定性的側面として退職給付のそもそもの意義を再確認し、給付設計の考え方をもう一度整理してみる必要がある。また、定量分析として「均等補正」を行った場合と行わない場合のPBOを比較検討する必要がある。
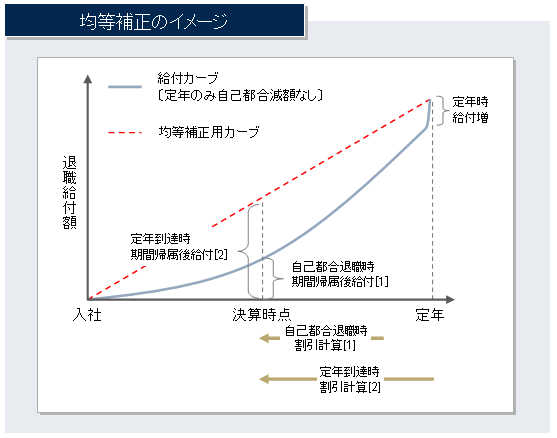
ここで、均等補正のイメージをつかむために、ごくシンプルな説例を用いてその一手法を紹介したい。退職給付としては、比較的よく見かける自己都合減額を有する制度における均等補正を考える。上図に示すように、59歳時で自己都合退職する場合と60歳時で定年退職する場合とで給付カーブに乖離が生じるものとする。「均等補正」を行わない「給付算定式基準」による期間帰属では、59歳までは給付カーブに沿って緩やかに費用化が図られ、59歳から60歳の1年間で定年到達による給付増加部分の費用化を一時に図ることになる。
こうした過度な費用の先送りを避けるべく、定年到達による給付増加部分も予め事前に費用化を図るように「均等補正」を行う必要がある。上図では、赤い点線が均等補正用のカーブとなる。それぞれ退職確率及び定年到達確率を加味した上で、自己都合退職においては[1]の金額が、定年到達においては[2]の金額が、PBO算出時における割引計算の対象となる。
上図から想像可能なとおり、このようなケースにおいては、定年前と定年到達時で退職給付を2分割して、定年前給付に関しては「給付算定式基準」を、定年給付に関しては「期間定額基準」を採用するものとして計算を行えば、あらためて均等補正用カーブを設定することは不要となる。このため、上述のような給付設計では比較的短期間で定量分析を終えることが出来るが、実際にはそのようなシンプルな給付設計ばかりではなく、給付カーブのピークがもう少し若年層であるケース、昇給傾向が給付カーブに大きく影響するケース等、簡単には割り切れない場合も多々ある。
「給付算定式基準」を採用する場合には、そもそもの「均等補正」の必要性の有無、あるいは具体的な「均等補正」の織り込み方等、各社の実態に応じて主体的かつ合理的な判断が求められることになり、新退職給付会計基準の原則主義としての特徴を強く実感することになる。
5.スケジュールを中心とした実務対応
通常、退職給付会計コンサルティングでは、今回焦点を当てた「退職給付見込額の期間帰属方法」と「割引率の設定方法」の2つの組み合わせを検討することになる。このため、会計監査人との調整を含めて4~5回程度のミーティングを行うケースが多いが、シンプルな制度で3カ月、厚生年金基金など複雑な制度で6カ月程度のコンサルティング期間を要する。
今回の基準改正に伴い新旧PBOの差額を財務諸表に計上するタイミングは、2014年度の期首、もう少し実務的に言えば、2014年6月末の第1四半期となっている。なお、「どのような計算前提でPBOを算出するのか」判断が付きかねている場合も含めて実務上の対応が困難な場合には、四半期財務諸表でその理由を注記することを条件に2015年度の期首からの適用が認められている。
ただし、この場合には、2015年3月末に新PBOの概算額を注記する必要がある。2015年3月末に概算額、2015年6月末に正値を求めるスケジュールは実務的でないため、この場合には2015年3月末に正値のPBOを求める必要があると考えられる。従って、実質的には9ヵ月の先延ばしとなる。
コンサルティングサービスを提供する受託機関サイドの都合で言えば、PBO計算の繁忙期を迎える下期はサービスの供給量にも自ずと限界がある。このため、企業が「各社の実態に応じて主体的かつ合理的に選択した計算前提に基づいた新PBO」の算出を相談するタイミングは、2013年度上期に集中することになる。このタイミングを逃すと、事前の把握なしに、いきなり新旧PBOの差額を財務諸表に計上、具体的には期首の利益剰余金に加減することになる。また、もし計算前提を指示できる状況になければ、実際には新PBOの算出すら不可能といった事態も想定される。
こうした事態を避けるべく、IFRS適用に関して、ある程度割り切った考えのもと、想定されるリスクを許容して、現行と同じ「期間定額基準」を採用することは可能である。また、そこまでの割り切った判断が難しい場合には、2014年度中は1年間様子を見て各社の適用状況を公表データから分析するといった対応も考えられる。本来であれば、十分な検討を経て、2014年6月末までに対応を終えることが望ましいと考えるが、現時点までの各社の対応状況を概観する限り、一定のリスクを覚悟の上での「期間定額基準」の採用や、1年遅れの適用が現実味を帯びてきたと思える。
(※1)計算を委託する企業の立場からみて半自動的ということであり、受託機関の立場からは専門家として細心の注意を払い、適正な計算手法を組み合わせてPBOを算出している。
(※2)形状としてはS字給付カーブであっても若年者が多数を占める等、人数ウェート等を考慮した結果、下に凸とみなせるケースを含む。
(※3)紙面の都合上、適用スケジュール等については、3月末決算企業に関する取り扱いを記載している。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。