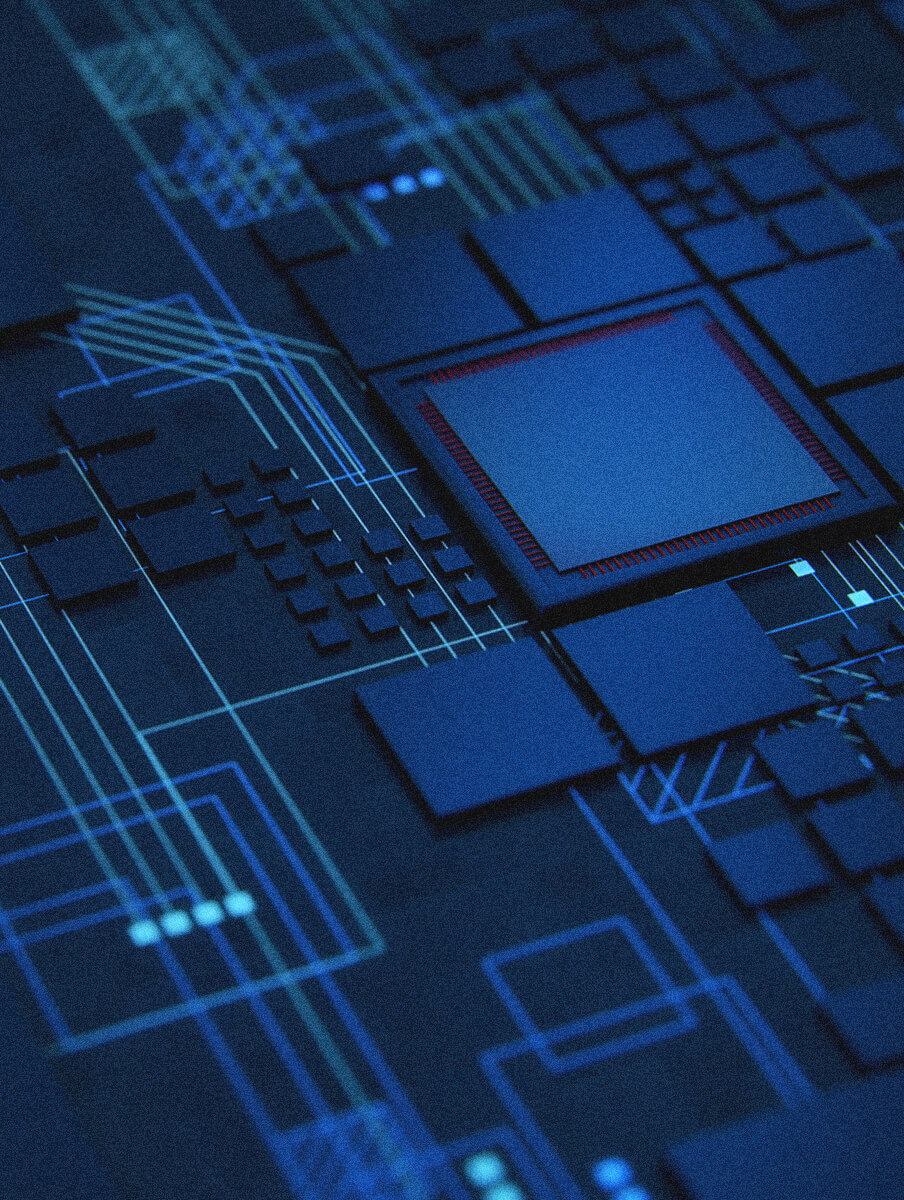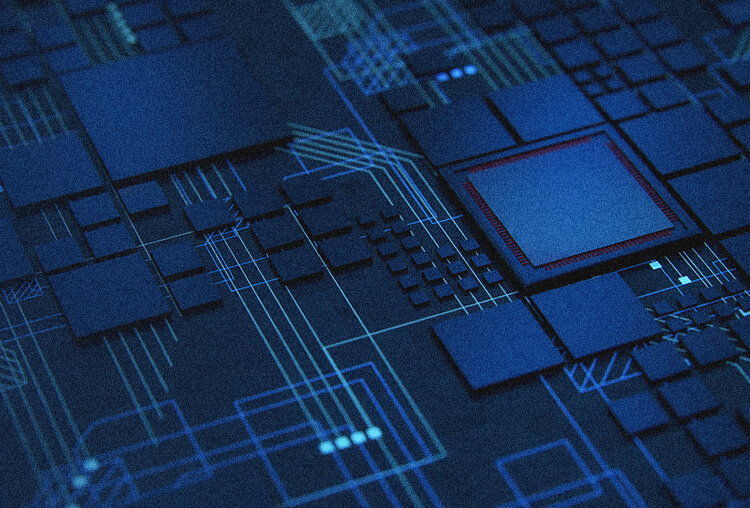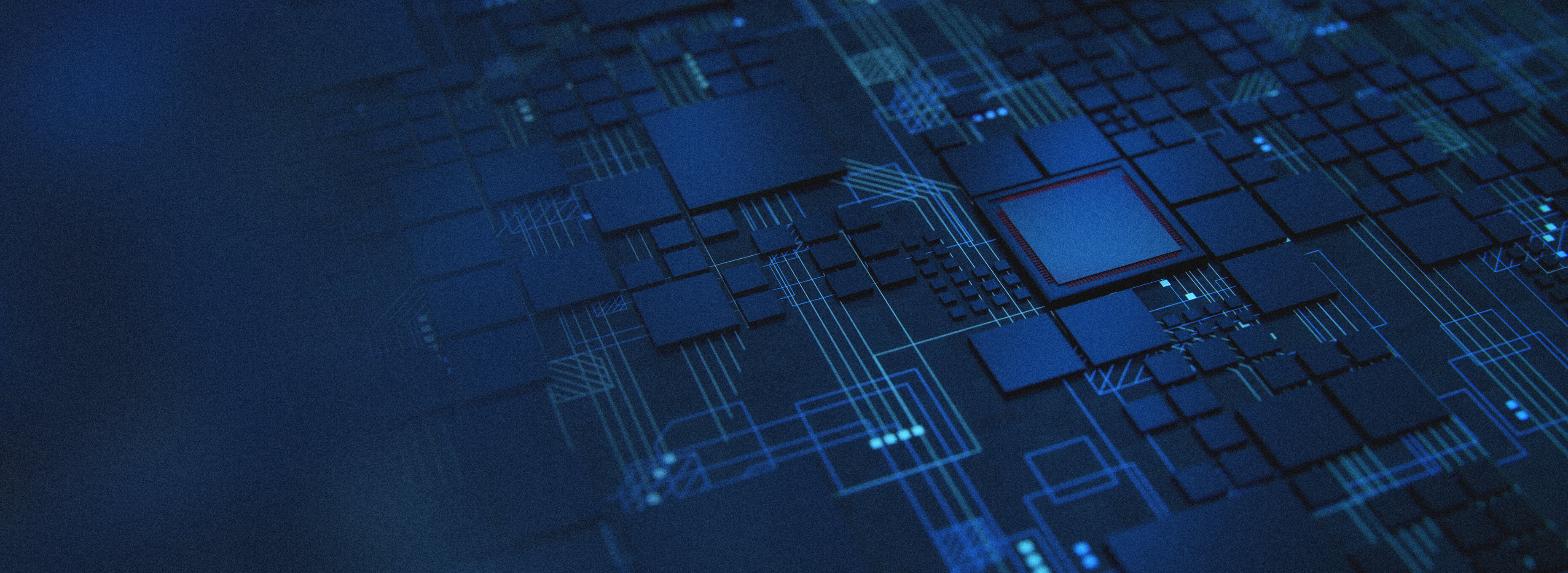「財政再建」と「デフレ脱却」は矛盾する政策目標か?
2015年02月16日
安倍政権における経済政策の目標は財政再建とデフレ脱却の二本柱であり、これらは日本経済が抱える最も重要な課題でもある。しかしこれらは、時として互いに背反する二つの目標として捉えられ、いずれを優先するかという二元論に帰着する(そして多くの場合、財政再建よりもデフレ脱却が優先される)。実際、2014年度より実施された消費税増税(5%→8%)が日本経済に与える影響が想定外に大きかったこともあり、景気回復・デフレ脱却を確実にするためとの名目で、2015年10月に予定されていた10%への再増税は、2017年4月に延期されることが決定された。
確かに財政再建に必要となる歳入増、歳出減、あるいは双方の組み合わせは、短期的には景気に対してマイナスの影響を与える。景気の減速は物価の上昇を抑制する効果があることから、これはデフレ脱却という目標と背反するように映るのも無理はない。しかし目指すべき目標は単年度での瞬間的なインフレではなく、構造的・安定的なデフレ経済からの脱却である。
また、そもそも拡張的な財政出動は、デフレ退治という意味において本質的な効力を持つとは考えにくい(※1)。財政政策は短期的に景気を底上げすることは可能かもしれないが、永続的に拡張財政を行うことはできないためだ。いずれ歳入増、歳出減、あるいは双方の組み合わせによる財政再建が必要となる以上、そのタイミングにおいてマイナスの影響は不可避となる。本当に拡張財政でデフレ脱却が可能であるなら、裏を返せばその先にある緊縮財政によりデフレ回帰が生じることになる。これは異時点間の所得分配によって徒に世代間格差を拡大させる効果しか持たない。
いわゆる「乗数効果」や「ワイズスペンディング」による成長力の押し上げも、この誹りを免れない。そもそもこうした「上げ潮」的な考え方は、20年以上に亘って放漫財政と景気停滞・デフレが併存し続けてきた歴史により否定されている。デフレの真因は長期停滞を招く潜在成長率と自然利子率の低下にあり、ケインズの「流動性の罠」で想定されているような一時的需要ショックに対応しても問題は解決しないとの見方がより一般的となりつつある(※2)。
他方で、そもそも財政再建を急ぐ必要はないとする意見も一部にある。確かにデフレ、経常収支黒字、ホームバイアスの三点セットで日本人が国債を買い続ける中、財政状況が悪化の一途を辿る中でも低金利が続いている。しかしこの前提は非常に脆弱だ。第一に、デフレ脱却が視野に入った段階で金利が上昇する可能性がある以上、それ以前に財政再建の目途をつけておかなければならない。第二に、高齢化に伴う家計貯蓄率の低下により、近い将来における経常収支の赤字化が視野に入っている(※3)。第三に、ホームバイアスは人間の心理に依存する不確かなものである。財政再建が絶望的であると市場が判断した瞬間に金利が急上昇し、市場の自己実現性により低金利均衡から破綻均衡にジャンプするという突発型のリスクが存在することは、近年のギリシャの経験などが実証している。
従って財政再建とデフレ脱却の二つの目標は、背反する両立不可能な対立概念として捉えられるべきではなく、むしろ同時に達成されることが望ましい。2014年12月の衆院選を受けて改めて今後4年間の政策運営を担うことになった安倍政権が、より本格的にこれらの目標に取り組むことを期待したい。以上のような議論を網羅的に踏まえ、弊社では2月3日に「日本経済中期予測(2015年2月)—デフレ脱却と財政再建、時間との戦い」を発表した。是非ご一読いただければ幸いである。
(おすすめ関連レポート)
日本経済中期予測(2015年2月)-デフレ脱却と財政再建、時間との戦い
日本経済中期予測(2015年2月)解説資料-デフレ脱却と財政再建、時間との戦い
(※1)こうした主張の中で最もナイーブなものは「リカードの中立命題が成立すると仮定すれば、家計など経済主体は将来的な増税を予期して支出を抑制するため、経済には中立的である」という主張である。もちろんリカードの中立命題は強すぎる仮定であり、多くの理由から成立しない。だからこそ今回の消費税増税のような政策変更が短期的な経済には影響を与えるわけでもある。
(※2)詳細は小林(2015)「日本経済見通し(2015-2024年度)—デフレ脱却と財政再建、時間との戦い(日本経済中期予測第2・4章)」参照。
(※3)ただし経常収支はフローの概念に過ぎず、より本質的な問題は対外純資産の動向にある。詳細は小林(2014)「「経常収支が赤字化したら財政破綻」は本当か?」参照。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。