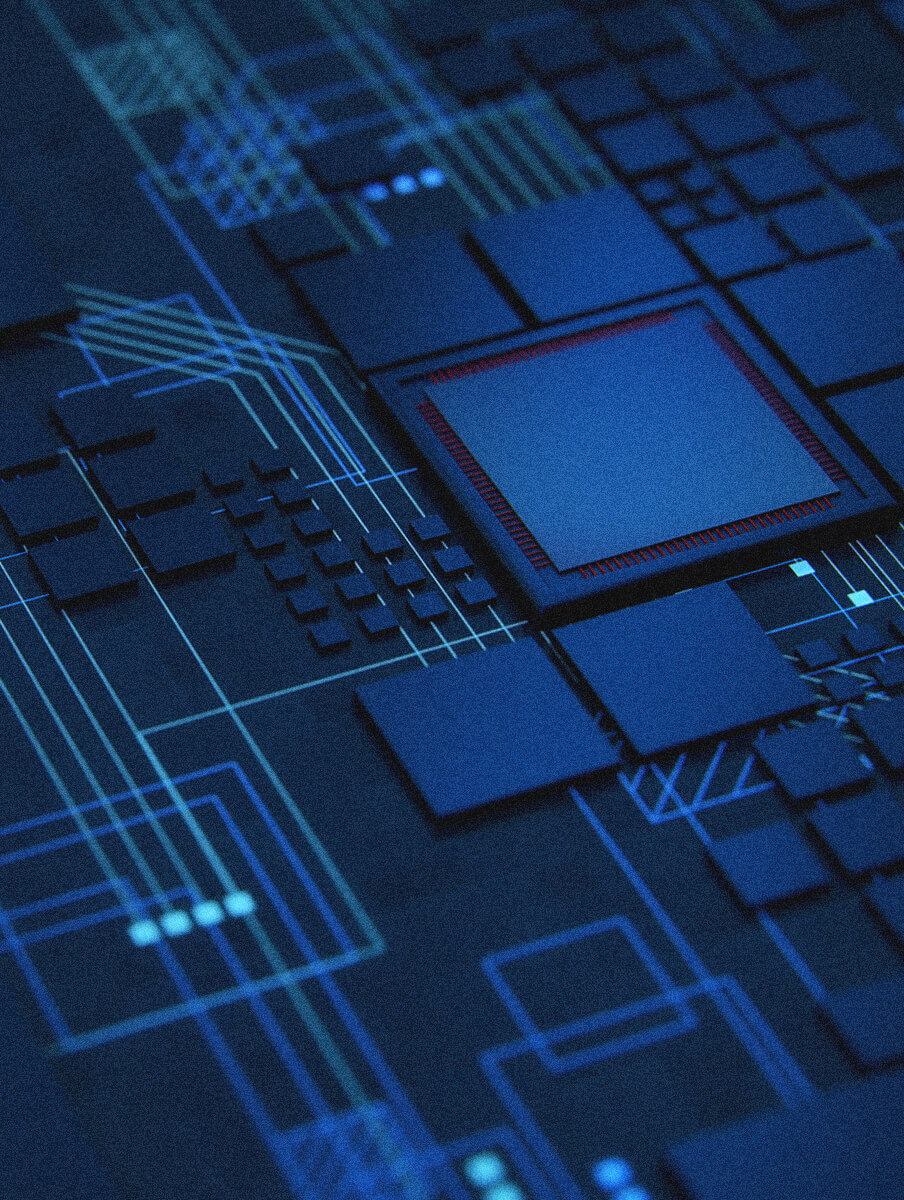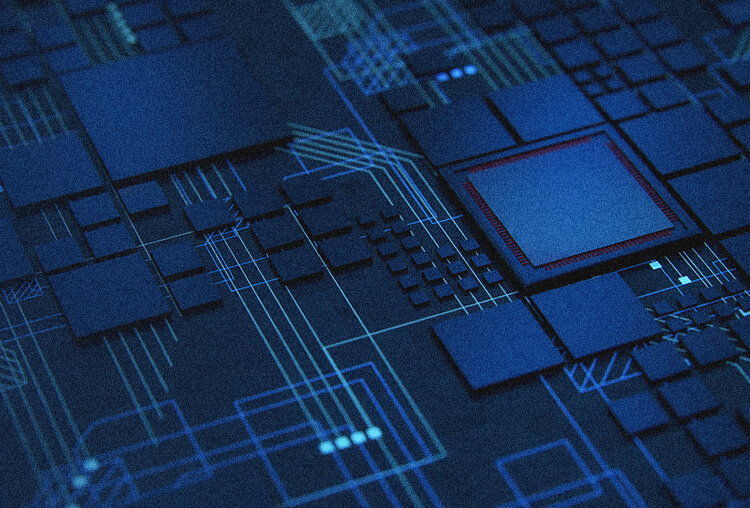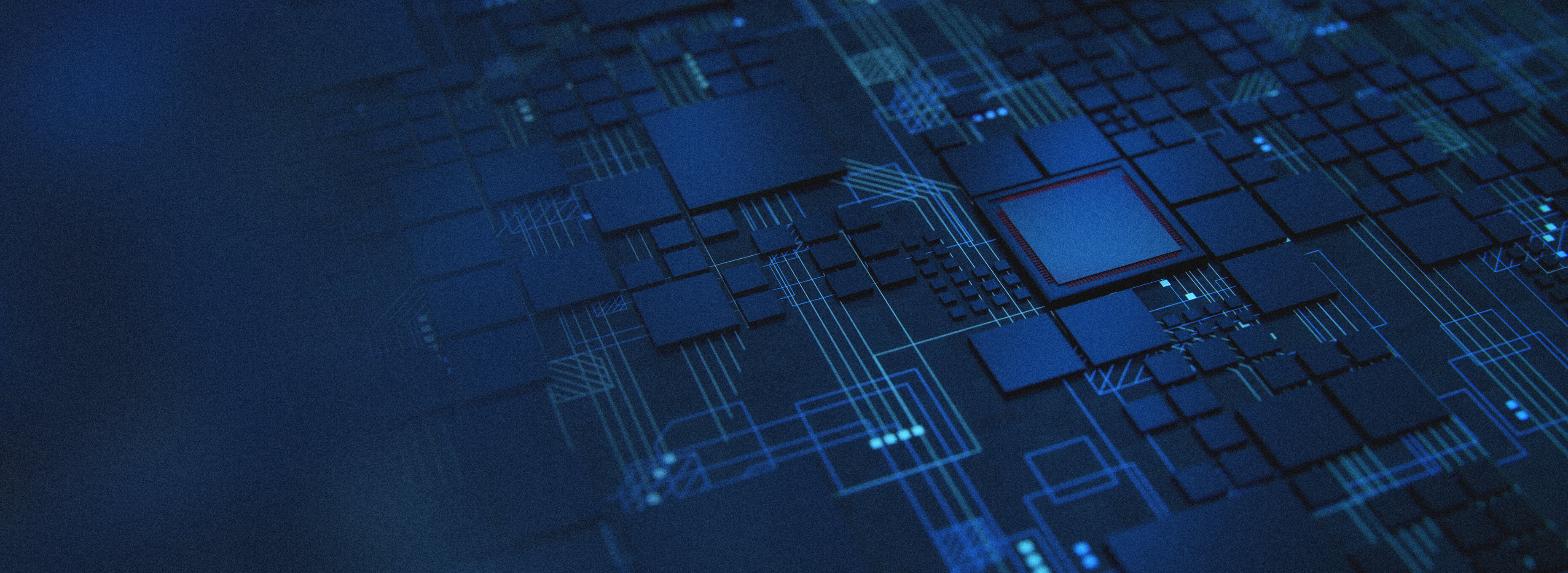ロンドン報告 2011年盛夏 高品質の「サービス」を売るということ
2011年07月13日
かつて、次のような趣旨のレポートを書いたことがある。
—日本の製造業の生産性向上ペースは速い。日本の競争力の源泉であり、趨勢的な円高はその自然な結果である。ではサービス産業はどうか。当たり前だが、テレビやパソコンの技術進歩とそれに合わせた労働生産性の向上に、理髪店やタクシーの生産性が追いつくわけはない。しかし70年代初頭までの完全雇用などもあって、生産性が一向に上がらない企業、業種の賃金も総じて製造業同様のペースで上昇してきた。それはサービス産業の単位労働コストを上昇させるが、非貿易財産業であるサービス産業を業態ごと淘汰するメカニズムは存在せず、結果として、高コスト体質が出来上がる—
業種ごとの日米生産性比較などを行ったうえでの議論であり、大まかな理屈としては間違いではなかったと思う。しかし、大きな見落としもあった。それは日本的サービスの質の高さである。
在英日本人の多くが、家探しに日系不動産会社を使うのは、言葉の問題よりも入居後のアフターサービスに現地系との隔絶たる差があるからである。現地不動産会社の場合、やや大袈裟に言えば、入居が決まって契約書にサインした瞬間にこちらは客ではなくなるケースが少なくない。似たようなことは引越し業者や内装工事業者などでも言える。現地系の多くは、搬送中に家具が破損したり、工事中に私物が紛失するリスクには、依頼者が保険をかければいいという構えである。破損を避けるための工夫がないとは言わないが、日系業者に比べれば、その意識が乏しいように見える。
日本の理髪店では「1000円カット」であっても、簡単な洗髪をしてくれるか、少なくとも掃除機のようなもので切った髪を吸い取ってくれる。英国では代金が10ポンドだろうが20ポンドだろうが切りっぱなしだから、どこかへの行きがけに髪を切るということができない。理髪店に行くのは、家に帰る直前でなければ非常に面倒なことになる。
実のところ、日本のコアコンピタンスは、サービスの質の高さなのだ。製品レベルの質の高さはいずれ他国企業にキャッチアップされる。しかし、サービスの質の高さにおいて、日本の後を追っているような競争相手は見当たらないといってよいのではないか。
英国を含めた海外に進出しているサービス産業は少なくないが、残念なのは現地化を志向する中で、いつの間にかサービスの質も現地見合いになってしまう例が散見されることだ。例えば、ある程度の品質を確保すれば、放って置いても寿司は売れる。しかし、売り物が寿司という商品だけでは、いずれ現地企業に真似される。そういう進出の仕方が多いのだが、真に売られるべきは日本の寿司屋で供されるサービスではあるまいか。
もちろん例外もある。最近、ある昼食会で大手日系サービス企業の英国法人社長のお話を伺う機会を得た。この会社はマネージメントを徹底的に現地化する一方で、サービスの質は日本的を貫き、その質の高さの認知に成功しているという。当たり前だが、重要なのは、この「認知される」ということだ。日本的サービスを当たり前と思っている在英日本人だけを相手にするのではなく、英国的サービスを当たり前と思っている英国人の意識転換を導くことで、高品質サービスを日本の有力な輸出分野に仕立てることができる。ここに高い壁があるのだが、同社はそれに成功している。
結局、冒頭に紹介した議論の不備は、製造業で言う生産性、つまり一定の質の製品を一定量生産するための労働投入量といった分かりやすい概念を、サービス産業に当てはめたこと、もう一つはサービス産業を非貿易財産業と割り切ってしまっていることにあるのであろう。例えば4000円の散髪代と20ポンド(2600円)の英国の散髪代とを収斂させる経済的メカニズムは存在しない。確かにサービス産業の多くは非貿易財産業なのだが、企業が外に出れば話は変わる。日本のサービスの質に対し、30ポンド強の価値を認めてもらうことは英国でも可能かもしれない。ただし、そのためのマーケティングは、徹底的な現地化が必要な分野なのだろう。
上に挙げた某日系企業のような成功例が増えれば日本は変わり得る。往々、産業政策はまともにワークしないと評されることが多いが、それは一つに市場の諸力で決まる成長産業を人や政府が事前に見極めることが「定義により」不可能なためである。しかし、現存しているサービスの優位性を政策的・戦略的に海外に売り込んでいくことは相対的に容易であるかもしれない。TPPやEPAの推進に際し、日本のコアコンピタンスを売るという視点をぜひ取り入れて欲しいものである。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。