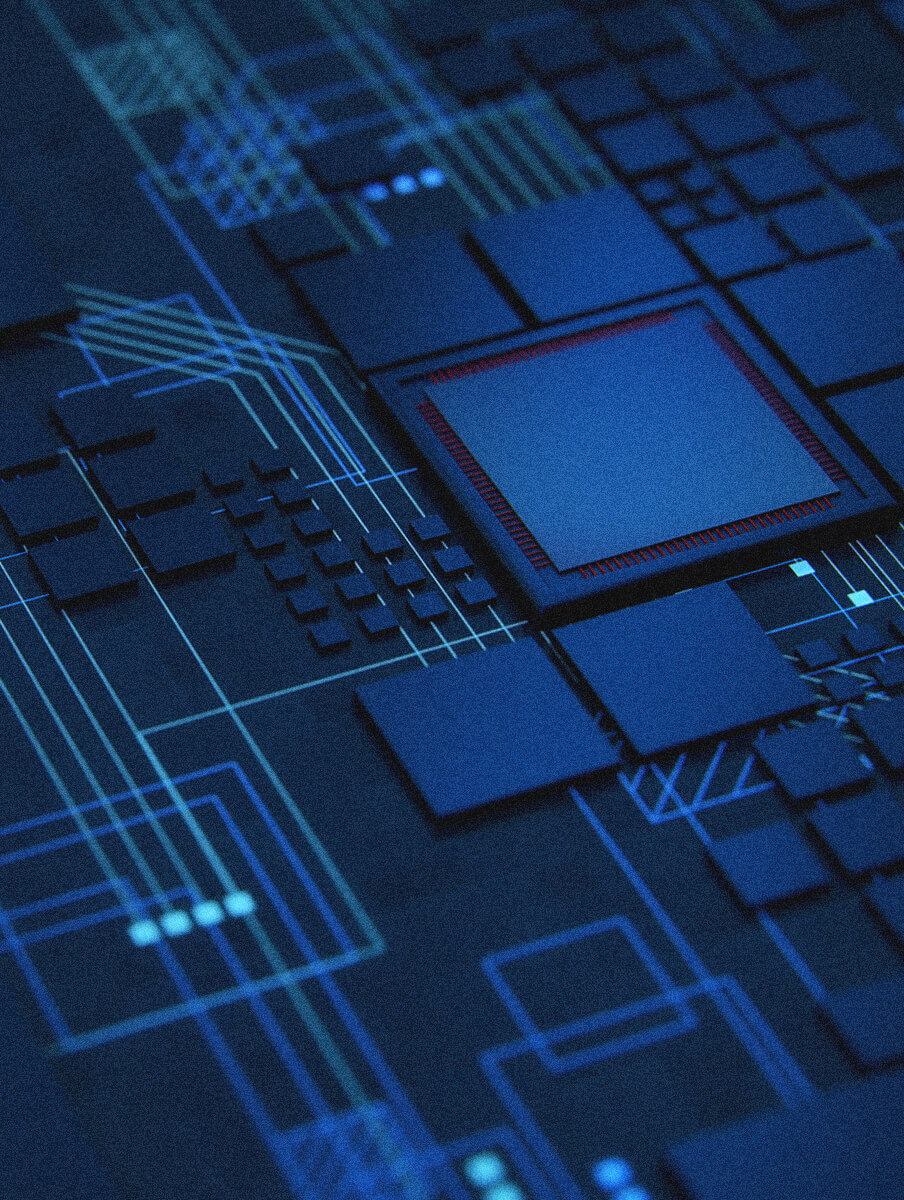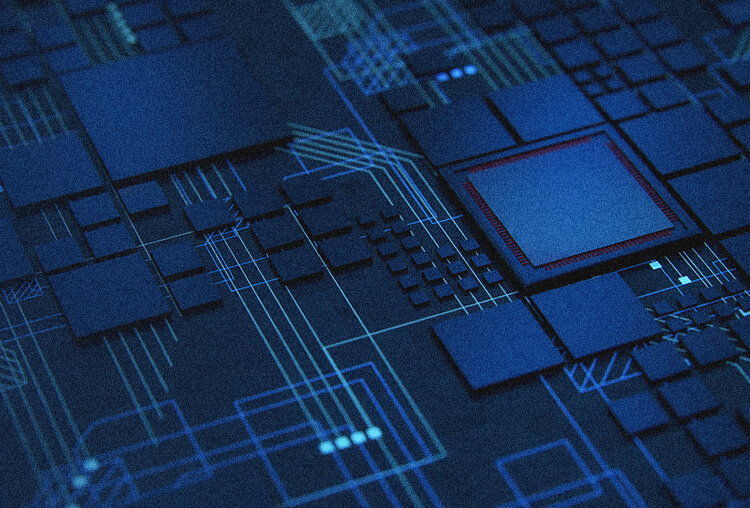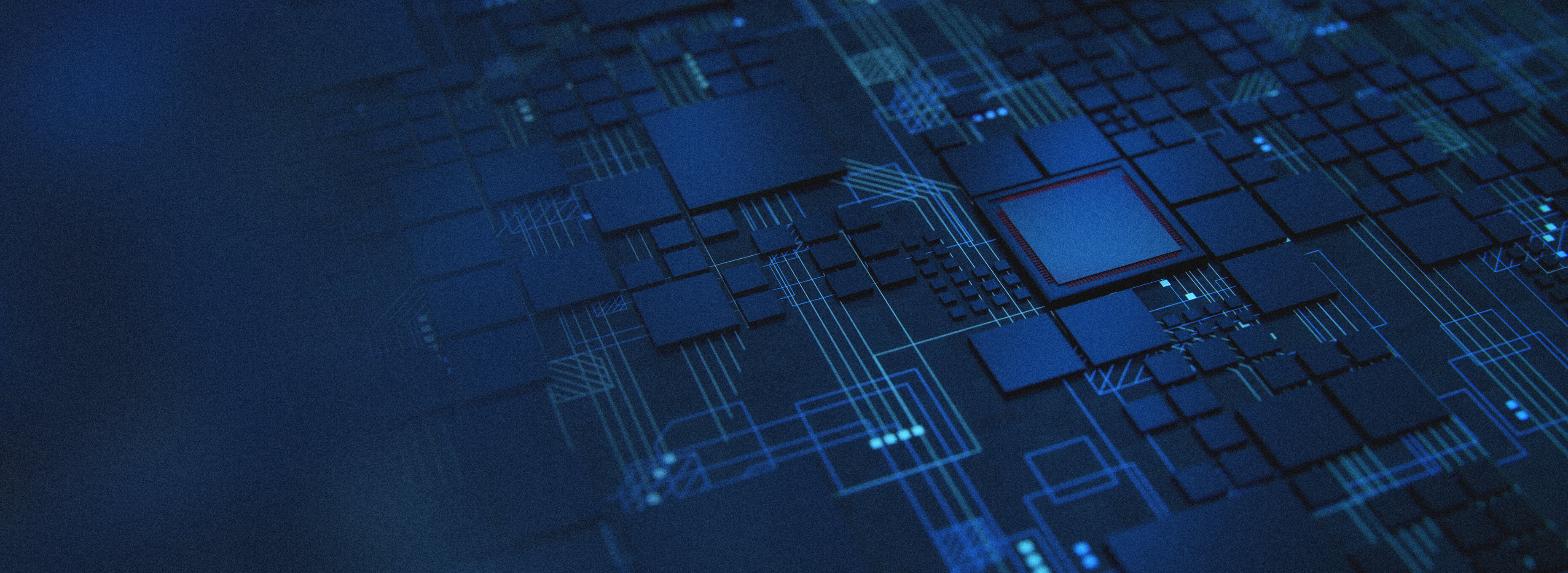2017年12月20日
「他の機関投資家と協働して対話を行うこと(集団的エンゲージメント)が有益な場合もあり得る。」(指針4-4)とする日本版スチュワードシップ・コード改訂が決まったのは2017年5月だ。耳慣れない言葉だが、集団的エンゲージメントとは、複数の機関投資家が、投資先企業との建設的な目的を持った対話を協働で行うことをいう。半年たった今、国内の機関投資家の間でも、新たにコードに記されたこうした行動へ積極的に取り組もうとする動きが表れている。
一つ一つの機関投資家が個別に企業に働きかけても、持ち株数が少なくては企業を動かす力として弱い。そこで、多くの機関投資家が協働することで、力を強めていこうというわけだ。「目的を持った対話」の具体的な内容は様々だろうが、企業ガバナンス問題をはじめ、たとえばCO2削減やダイバーシティ推進等をテーマに機関投資家が投資先企業と対話し、変化を促すことが想定される。集団的エンゲージメントへの期待が高まるのもわからないではない。
しかし、こうした取り組みが、期待とは異なる結果を生む可能性も考えておくべきだろう。
ある産業分野の同業者X社、Y社に対する株式保有の状況が、
機関投資家A→事業会社X
機関投資家B→事業会社Y
であれば、X社とY社は互いに競い合い、それぞれの株主に高いリターンを返していこうとするだろう。「機関投資家A・B→事業会社X」であっても、X社は他社と競い合いながら企業価値を高めていこうとする。
では、「機関投資家A→事業会社X・Y」ではどうだろうか。Aの株式保有量の大きさによっては、持ち株会社の下に同業の事業会社が2社あるのと同じ状況になる。この場合、X社とY社は、競争ではなく協調を選ぶかもしれない。市場のすみわけや価格統制で、利益を最大化する方法もあり得るのだ。
「機関投資家A・B→事業会社X・Y」でも競争は抑制されるだろう。特にA・Bの間に協働関係があれば、単一の持ち株会社の場合と同様に考えられる。
X社、Y社と競争するZ社、P社、Q社があるならば、競争は維持されるだろうが、寡占市場の場合、株式の保有構造によっては、A・Bの協働関係がX社とY社の競争を阻害する要因となり得る。
最近の米国の研究では、機関投資家(A・B)が同業の事業会社(X・Y)の株式を保有する状況を指して、水平的株式保有(horizontal shareholding)と名付け、競争抑制的作用があることを指摘するものがある(※1)。これらの研究によれば、寡占的な産業分野で水平的株式保有がある場合、X社とY社は財・サービスの販売数量を絞り、価格を高く維持することで利益を上げようとするだけでなく、販売数量が少なくて済むので、設備投資や雇用を拡大することもなくなるという。また、X社とY社の経営者報酬は、個々の企業の業績ではなく、X社とY社のトータルの業績に連動するようになるとも指摘されている。実質的持ち株会社の下での協調が経営成果を測る指標となるということだろう。
これから始まるわが国の集団的エンゲージメントで、どのような対話テーマが選ばれるかわからない。しかし、もしかすると集団的エンゲージメントの成功は、消費者が企業に払う財・サービスの価格を引き上げることとなるかもしれない。もっとも、そうすることで企業があげた利益は、配当や株価上昇によって、消費者それぞれが保有する金融商品(株式や投資信託等)の価値を上げたり、年金基金の積立金の拡大に帰結したりするのだから、消費者が損するばかりというわけでもない。
(※1)Elhauge, Einer, Horizontal Shareholding (March 10, 2016). 109 Harvard Law Review 1267 (2016); Harvard Public Law Working Paper No. 16-17.
Elhauge, Einer, The Growing Problem of Horizontal Shareholding (June 15, 2017). Antitrust Chronicle, Vol. 3, June 2017, Competition Policy International; Harvard Public Law Working Paper No. 17-36.
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
- 執筆者紹介
-
政策調査部
主席研究員 鈴木 裕