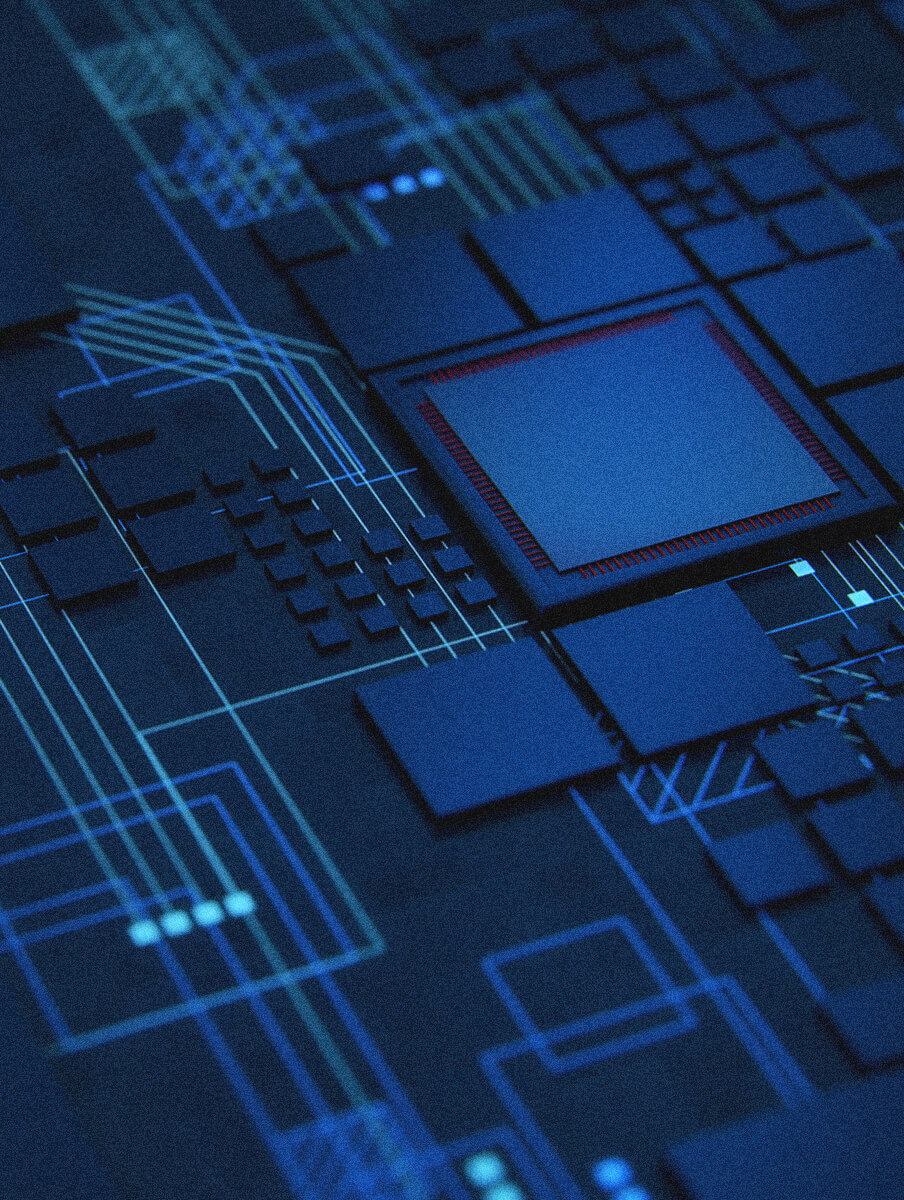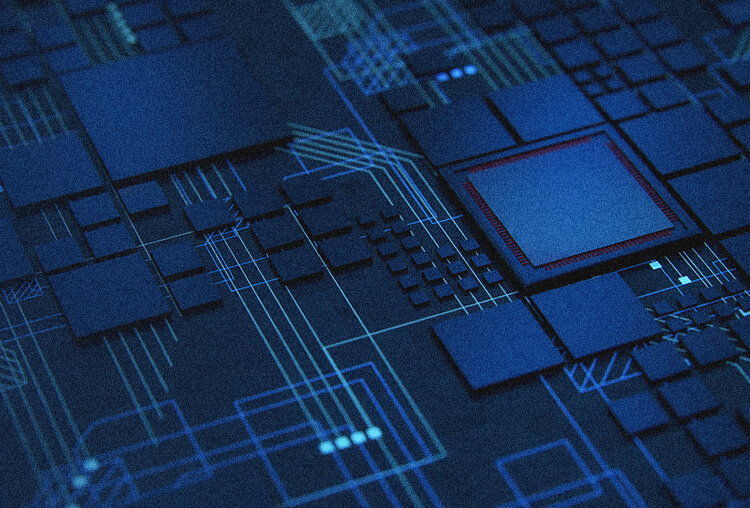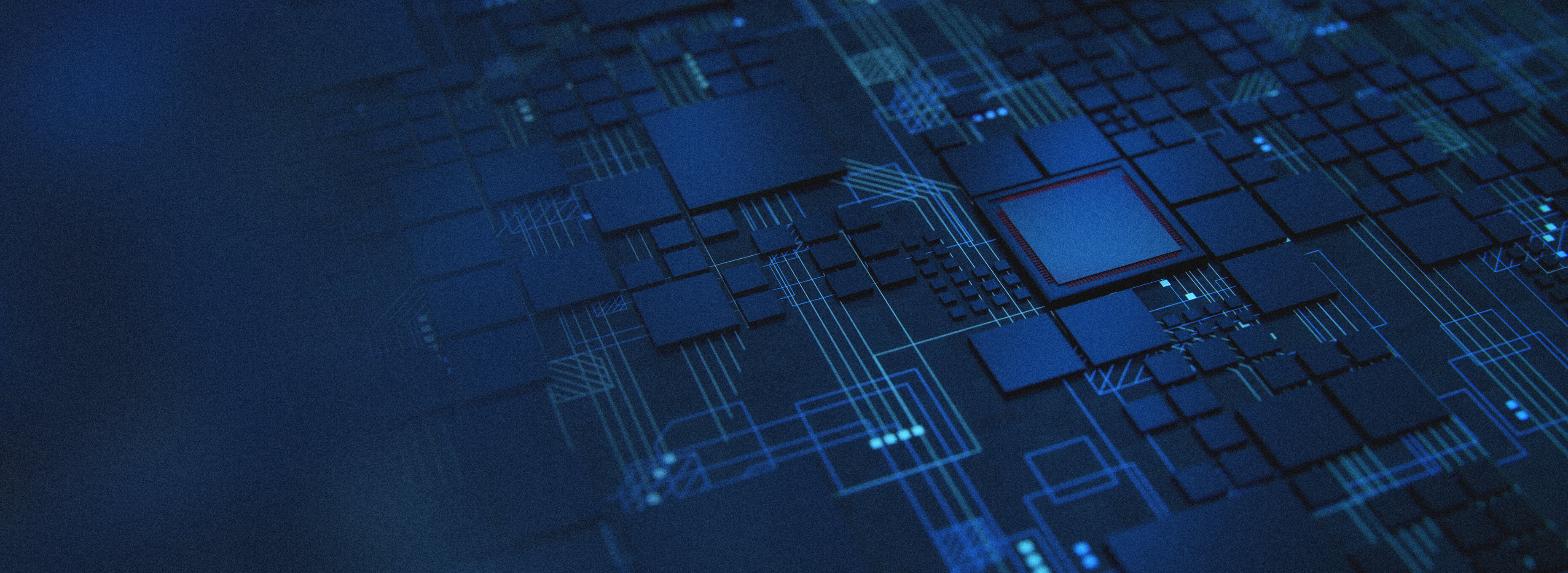2013年06月26日
6月中旬に行われたG8首脳会議後の欧州歴訪の中で、安倍首相は「アベノミクスによって日本の雰囲気は大きく変わった」と述べたと伝えられている。だが、変わりつつあった雰囲気が元の木阿弥になりつつありはしまいか、今問われるべきはこちらであるように思える。
経済の停滞が常態となって久しい日本においては、「変わるかもしれない」と人々に思わせること自体が難事である。それを成し遂げただけでもアベノミクスには相応の意義がある。政治は常に無策であるという諦観を一部払拭するとともに、この気分、雰囲気の変化が企業や家計の行動変化の起点ともなり得るからだ。同様の文脈から、人々が「やはり変わらないのか」と思い始めたとき、アベノミクスという戦略が失敗に終わる可能性が著しく高くなる。
似たようなことは、国際社会における日本のプレゼンスにも当てはまる、この半年間ほど、日本の政治、経済、金融市場の話題が欧米メディアを席巻したことは、少なくとも過去20年はなかったに違いない。このことはG8における安倍首相の発言のみならず、各種国際会議等における日本人の発言への注目度を高めてきたはずである。日本は経済力に比して政治力が弱いといわれ続けてきたが、経済力の顕著な低下によって両者が収斂するのを回避し、政治力(国際的発言力)を経済力相応に引き上げる、稀なる機会を得たということだ。問題は、この機会を本当に活かせるかどうかにある。
6月15日発行の英誌エコノミストは、—The third arrow of Abenomics, Misfire(打ち損じた第三の矢)—と題し、構造改革を伴う成長戦略の策定こそがアベノミクスの要諦であると指摘した上で、それが既得権への配慮などから骨抜きになる可能性があると警鐘を鳴らしている。仮に事態が同誌の指摘するままに推移すれば、まず起こることは、同誌はじめ、欧米メディアにおける日本のプレゼンスのフェードアウトである。応じて、日本の政治家、経済人の発言の重みも元に戻る。日本国内ではこれと平行し、「変わるかもしれない」という雰囲気が失われていくことになろう。そしてアベノミクスの失敗は強烈な教訓として残り、次に政治が「変わるかもしれない」という気分を作り出すことの困難は、著しく増すことになろう。
話は飛ぶが、最近の新興国をめぐる騒動も、気分や雰囲気がいかに大事であるかを示す典型例だ。米FRBの量的緩和の縮小観測が世界的に金融市場のボラティリティを高めているが、中でも目立つのが新興国通貨の下落である。
米国の政策転換はドル金利の上昇(期待)、ドル高(期待)を生む。それは新興国からの資本流出と裏腹の現象であり、しかもドル建て債務を抱える新興国を苦境に追い込む。こうした認識(というより通念)が新興国通貨の下落に拍車をかけているように見える。過去10年ほどの間に、多くの新興国が被援助国から被投資国に変わり、外貨建て債務の圧縮が劇的に進んだことなどは顧みられることがないかのようだ。恐らく、新興国にとっての不幸は、こうした外部環境の変調が、新興国の高成長シナリオに対する懐疑が強まる中で生じたことだろう。具合の悪いことに、通貨の下落は、広がりつつあった新興国の緩和モードに水を差し、早期の景気回復の可能性を低めてしまう。
景気停滞の長期化は、新興国の高成長シナリオへの懐疑をより強めることになろう。それは翻って、成長期待に触発された先進国等からの資本流入を阻害し、景気停滞の長期化を確実なものとしてしまう。気分と現実のスパイラルである。
新興国の苦境の発端は米国の金融政策転換にあった。新興国サイドにできることがないとはいわないが、例えばインドの対外開放積極化宣言やブラジルの高コスト体質是正宣言が、こうした外部環境の悪化を打ち消すことができるか、高成長シナリオの復活をもたらすかは疑わしい。
こうした自律性の欠如にさいなまれる新興国に比較すれば、日本は明らかに幸運である。「変わるかもしれない」という雰囲気を持続させれば、それは本当の変化の生みの親となる。さし当たっては、それに向け、太い第三の矢を放つことに注力すればよいのだから。
経済の停滞が常態となって久しい日本においては、「変わるかもしれない」と人々に思わせること自体が難事である。それを成し遂げただけでもアベノミクスには相応の意義がある。政治は常に無策であるという諦観を一部払拭するとともに、この気分、雰囲気の変化が企業や家計の行動変化の起点ともなり得るからだ。同様の文脈から、人々が「やはり変わらないのか」と思い始めたとき、アベノミクスという戦略が失敗に終わる可能性が著しく高くなる。
似たようなことは、国際社会における日本のプレゼンスにも当てはまる、この半年間ほど、日本の政治、経済、金融市場の話題が欧米メディアを席巻したことは、少なくとも過去20年はなかったに違いない。このことはG8における安倍首相の発言のみならず、各種国際会議等における日本人の発言への注目度を高めてきたはずである。日本は経済力に比して政治力が弱いといわれ続けてきたが、経済力の顕著な低下によって両者が収斂するのを回避し、政治力(国際的発言力)を経済力相応に引き上げる、稀なる機会を得たということだ。問題は、この機会を本当に活かせるかどうかにある。
6月15日発行の英誌エコノミストは、—The third arrow of Abenomics, Misfire(打ち損じた第三の矢)—と題し、構造改革を伴う成長戦略の策定こそがアベノミクスの要諦であると指摘した上で、それが既得権への配慮などから骨抜きになる可能性があると警鐘を鳴らしている。仮に事態が同誌の指摘するままに推移すれば、まず起こることは、同誌はじめ、欧米メディアにおける日本のプレゼンスのフェードアウトである。応じて、日本の政治家、経済人の発言の重みも元に戻る。日本国内ではこれと平行し、「変わるかもしれない」という雰囲気が失われていくことになろう。そしてアベノミクスの失敗は強烈な教訓として残り、次に政治が「変わるかもしれない」という気分を作り出すことの困難は、著しく増すことになろう。
話は飛ぶが、最近の新興国をめぐる騒動も、気分や雰囲気がいかに大事であるかを示す典型例だ。米FRBの量的緩和の縮小観測が世界的に金融市場のボラティリティを高めているが、中でも目立つのが新興国通貨の下落である。
米国の政策転換はドル金利の上昇(期待)、ドル高(期待)を生む。それは新興国からの資本流出と裏腹の現象であり、しかもドル建て債務を抱える新興国を苦境に追い込む。こうした認識(というより通念)が新興国通貨の下落に拍車をかけているように見える。過去10年ほどの間に、多くの新興国が被援助国から被投資国に変わり、外貨建て債務の圧縮が劇的に進んだことなどは顧みられることがないかのようだ。恐らく、新興国にとっての不幸は、こうした外部環境の変調が、新興国の高成長シナリオに対する懐疑が強まる中で生じたことだろう。具合の悪いことに、通貨の下落は、広がりつつあった新興国の緩和モードに水を差し、早期の景気回復の可能性を低めてしまう。
景気停滞の長期化は、新興国の高成長シナリオへの懐疑をより強めることになろう。それは翻って、成長期待に触発された先進国等からの資本流入を阻害し、景気停滞の長期化を確実なものとしてしまう。気分と現実のスパイラルである。
新興国の苦境の発端は米国の金融政策転換にあった。新興国サイドにできることがないとはいわないが、例えばインドの対外開放積極化宣言やブラジルの高コスト体質是正宣言が、こうした外部環境の悪化を打ち消すことができるか、高成長シナリオの復活をもたらすかは疑わしい。
こうした自律性の欠如にさいなまれる新興国に比較すれば、日本は明らかに幸運である。「変わるかもしれない」という雰囲気を持続させれば、それは本当の変化の生みの親となる。さし当たっては、それに向け、太い第三の矢を放つことに注力すればよいのだから。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。