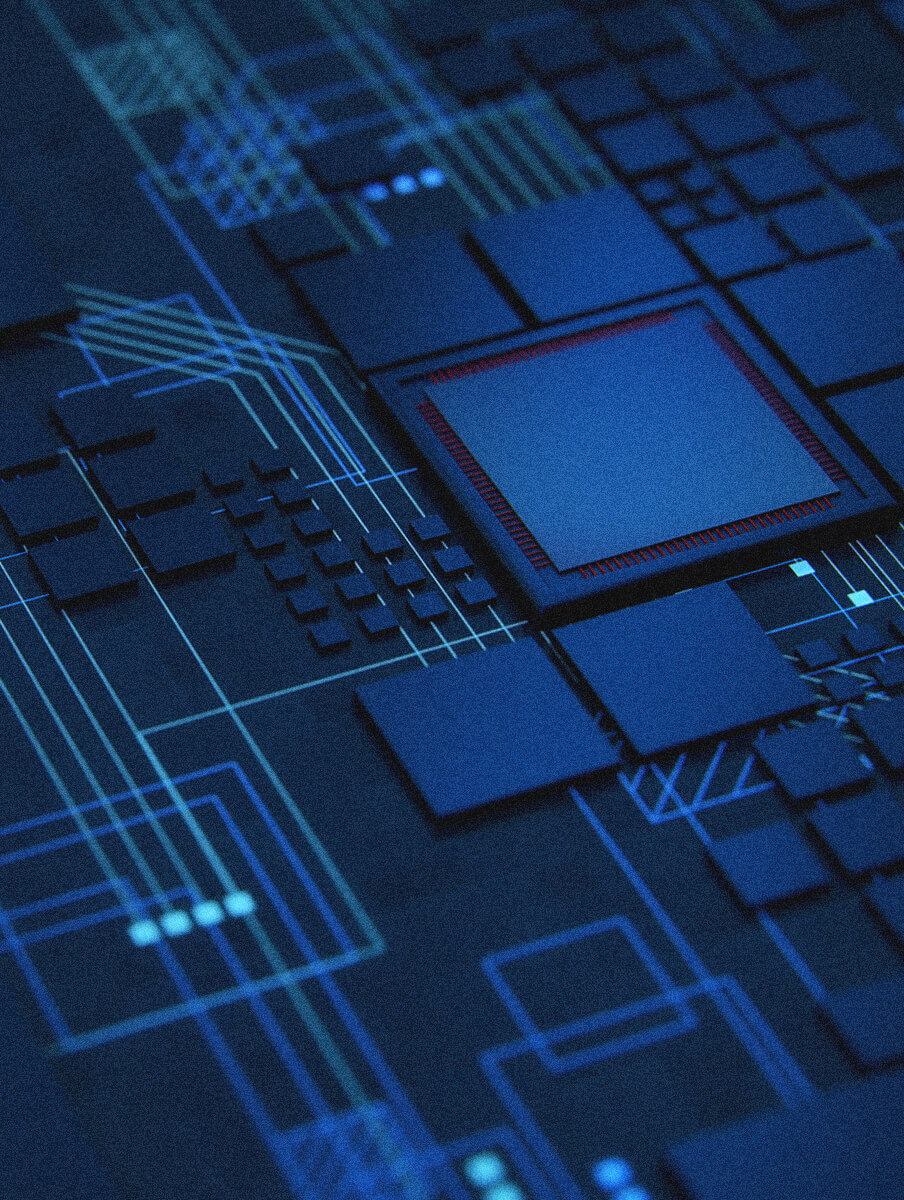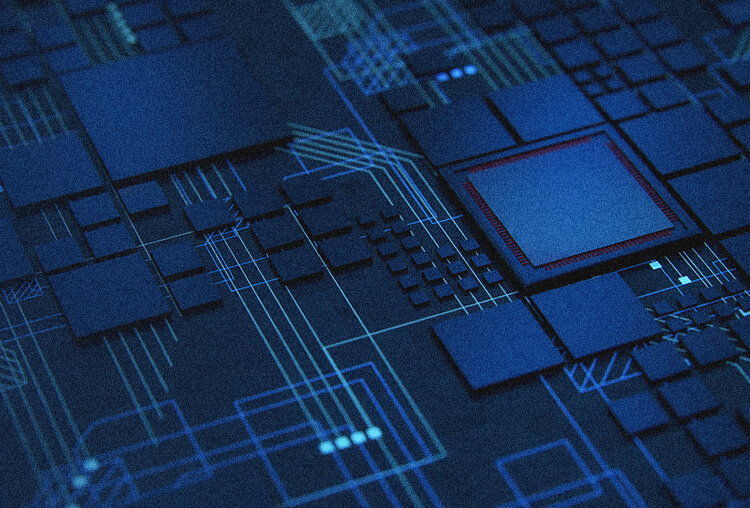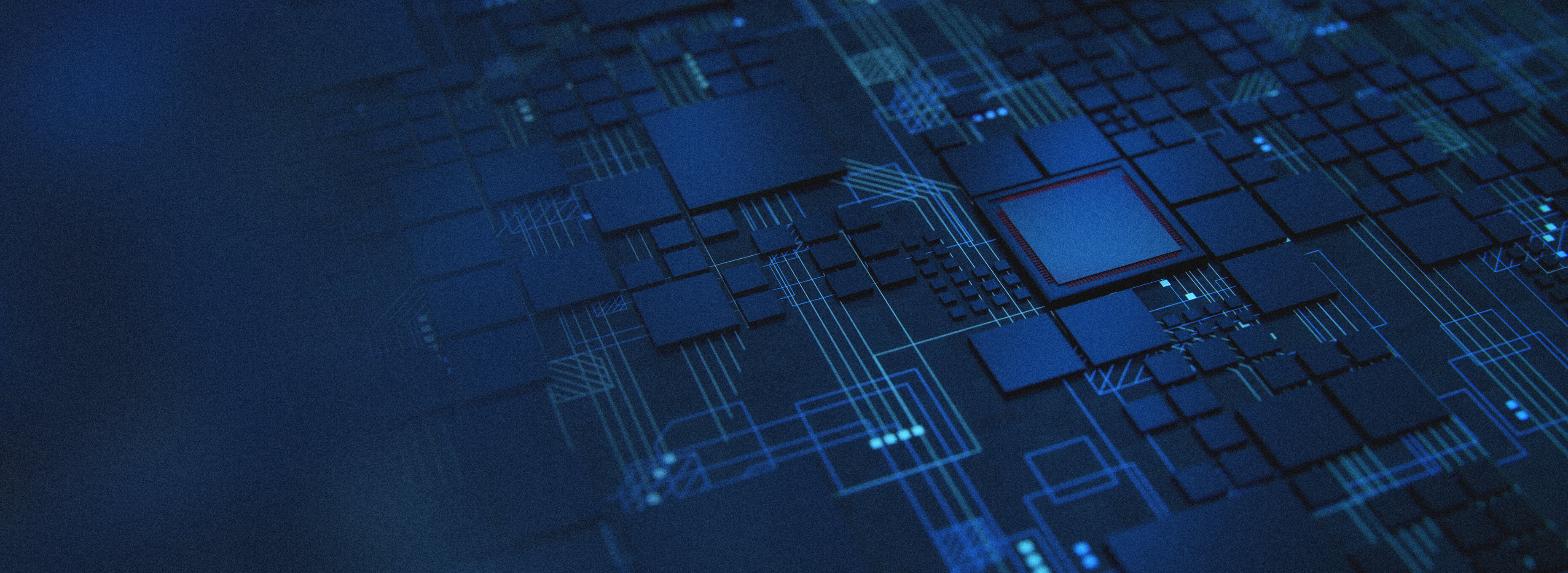「ロンドン報告 2013年、厳冬」 英国から見たアベノミクス
2013年01月24日
数日前、雪に凍えるシティを歩き、某経済メディアの主催によるイングランド銀行関係者の講演会を聞きに行った。開始を待つ間、同メディアの英国人記者と雑談していたのだが、彼がこんな質問をぶつけてきた。
「なぜ、円安が進んでいるんでしょう。これまでだって、日本政府は円安にしたくてたまらなかったのに出来なかった。なぜ、今回に限ってうまくいっているんでしょう?株高にも効いていますよね」
「多分、ひとつはタイミングが良かったんでしょうね。欧州のマーケットがおとなしくなっていて、リスク回避で円高というムードが消えている。日本の経常収支が目立って悪化し始めた。そんな時に出てきた話だから。日本の金融政策が本当に変わるかもしれないと思っている人も増えているのかもしれない。でも、それが良いことなのかどうかは分かりませんね」
幸い、講演の開始を告げるブザーが鳴り、会話は中途半端に終わった。自分の頭が整理されていなかったのだから、これは好都合であった。
1月18日にファイナンシャル・タイムズ紙が掲載した記事の副題「20数年ぶりに注目される日本(“Japan matters again, for the first time in more than two decades”)」が示すように、アベノミクスの登場と今に続く円安・株高が当地メディアを賑わすことが増えている。ガーディアンにはハーバード大学教授のM・フェルドシュタイン氏が「日本の成長戦略はすべて間違い(“Japan's growth strategy is all wrong”)」という少々刺激的なタイトルの論評を載せ、FTにはアダム・ポーゼン氏が「日本は景気対策を再考すべし(“Japan should rethink its stimulus”)」と題したコラムを寄稿している。ポーゼン氏は米国人エコノミストだが2012年までイングランド銀行の金融政策委員を務めた経験を持つ。
フェルドシュタイン氏はアベノミクスを「間違い」とするに当たり、より緩和的な金融政策はインフレを起こすかもしれないが、それは安倍首相が望む以上の急速なインフレであるかもしれないこと、劇的に低い長期金利のもとで初めて持続する政府債務拡大が不可能になり、この状況の破壊が実質金利を(投資家の要請により)上昇させる可能性があることなどを指摘している。そうであれば、インフレによる既存債務の実質価値の削減もおぼつかなくなるというわけだ。また、ポーゼン氏はすでにここまで政府債務が拡大した今、財政出動は便益よりもコストが大きく、より積極的な金融政策によるデフレ脱却と円高是正に注力すべきだと説いている。
一方、アカデミックなエコノミストではない、英誌エコノミストは「ケインズ、鉄道、そして自動車(“Keynes, trains and automobiles”)」と題した記事で、「アベノミクス」も結局はケインズ政策の焼き直しではないかと、その有効性に疑義を呈した上で、この政策が規制緩和や自由貿易の推進といった、より重要な構造改革を先送りする口実に使われるのではないかとの危惧を表明している。ポーゼン氏のように、金融緩和の積極化を評価する見方は散見されるが、総じて財政出動は評判が悪いようだ。
欧州では丸3年が経過したユーロ圏危機をめぐる政策論争がさまざまに繰り広げられてきている。「最終解」が財政統合を含む統合深化に尽きることは広く了解されながらも、そこに行き着くための政治的、社会的、経済的コストをどう抑制するかが難問なのだ。そうした中、比較的賛同者が多いとみられる考え方のひとつは、ユーロ圏の中でも財政状況に余裕のあるドイツ等は、緩和的な財政政策を取り、緊縮やむなしの財政危機国の調整コストを多少なりとも和らげるべし、というものだ。このような欧州からすれば、グロスの政府債務のGDP比がギリシャを優に超える日本における積極財政が、いかにも奇異に、危険に見えるのは至極当然であろう。
冒頭紹介した記者に限らず、英国でもアベノミクスとその帰趨に興味を抱く人は増えている。ただ、その多くが「何かがおかしい」と感じているようでもある。そうした彼らのもやもやはどこから来るのだろうか。日本の株高に慣れていないだけなのだろうか。円安・株高が持続することで、彼らがそれに慣れ、もやもやは自然に消えていくことになるのだろうか。そうではなく、円安が株高をもたらす局面が短期に終わり、円安は金利上昇と株安を伴う「日本売り」のさきがけであったことが判明し、彼らのもやもやが氷解するのだろうか。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。