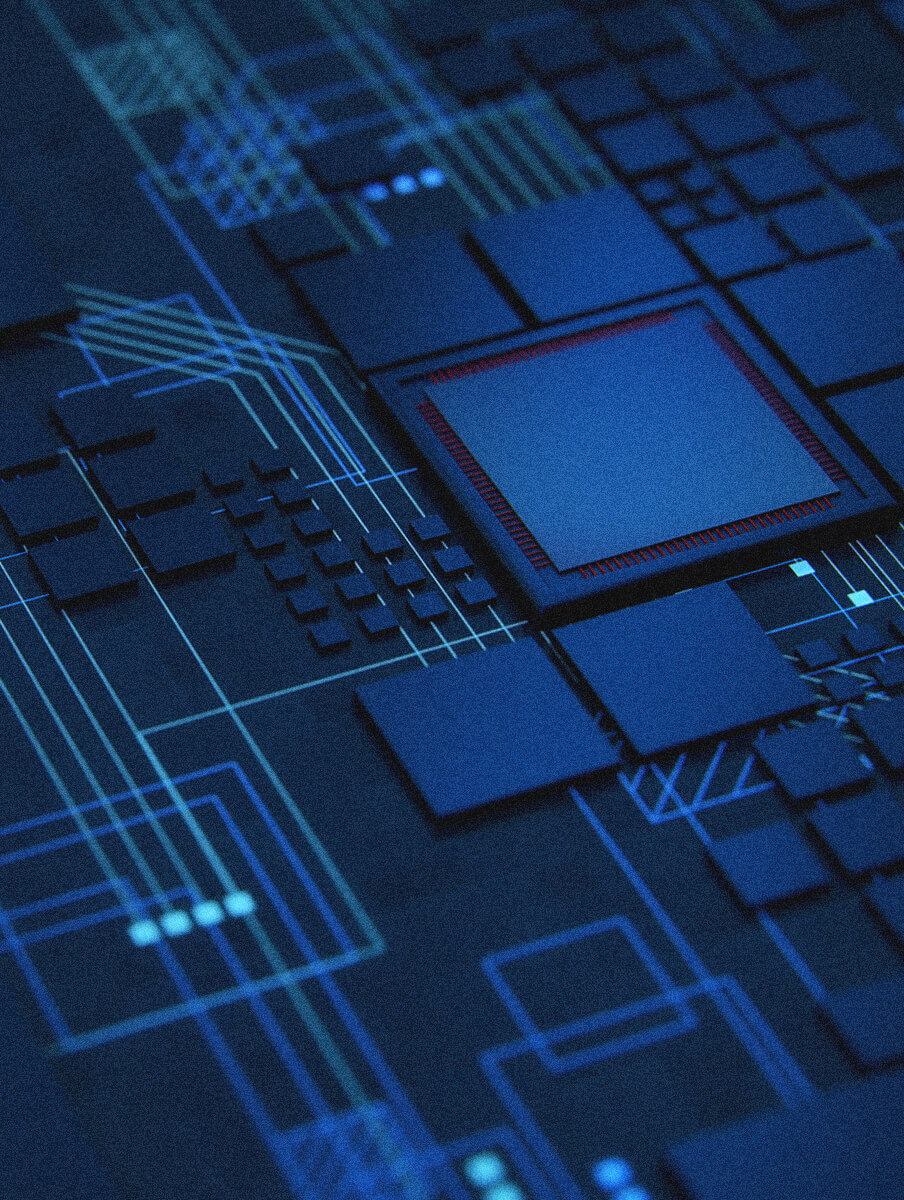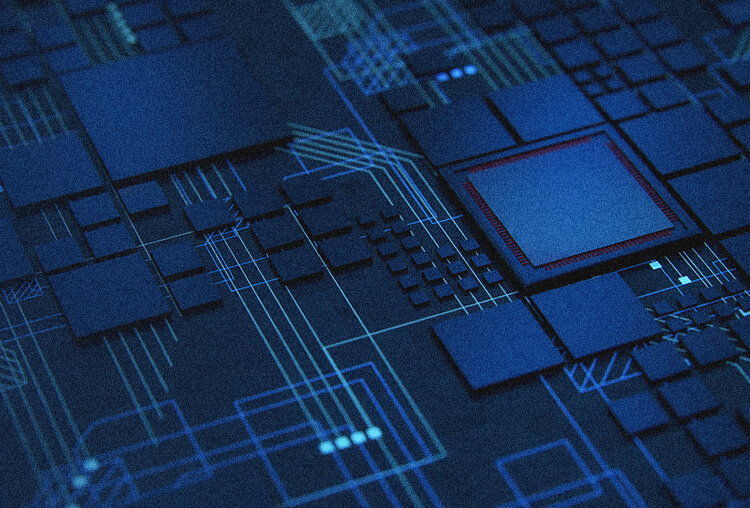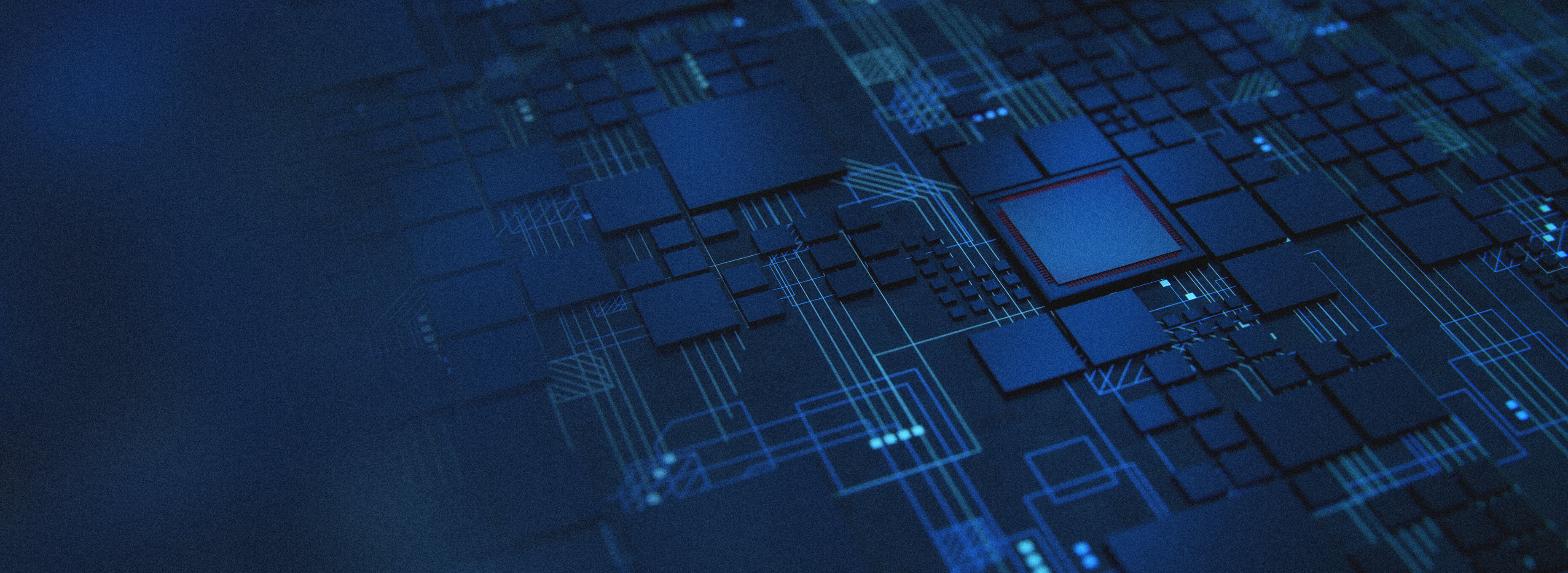「ロンドン報告 2012年、冷夏」 ロンドン五輪を前に思うこと
2012年07月18日
ダイアモンド・ジュビリー(エリザベス2世即位60周年)に先立ちリージェント・ストリートを覆っていた英国旗が万国旗に取って代わられた。21日には聖火もロンドンにやってくる。五輪開催が間近に迫っていることを思い起こさせる事例やニュースが増えている。
しかし、高揚感には今ひとつ欠けているように思える。五輪ではラグビーもクリケットもやらない。年齢制限のあるサッカーは、ユーロ2012よりも格落ちと見られてしまう。テニス熱は先のウインブルドン男子単のアンディ・マリーの活躍でピークに達した。こういう事情も多分にあろうが、多くのロンドン居住者にとっては開催期間をどううまくやり過ごすかが一番の関心事であるようにも思える。
ひとつには、テロの脅威が付きまとう。もちろん、周到な対策は練られているはずだ。だが民家の屋根にミサイルを設置するなどのテロ対策自体が、地域住民を半ば強制的に非常時体制に追い込んでいるし、2005年のロンドン同時爆破テロを身近な悲劇として記憶している人も少なくない。昨年夏の暴動は、テロであれ何であれ、いったん事があれば、便乗者が沸いて出て騒ぎを拡大させる素地がこの国にあることを示してしまった。
第二には、地下鉄などの公共交通機関の混雑、混乱が避けられそうにないことだ。ロンドン交通局によれば、例えば金融街シティに位置する地下鉄Bank駅は大会期間中のほとんどの日の夕刻5時から9時頃にかけて、乗車に30分以上の時間がかかるらしい。東京の通勤電車のような押しくら饅頭に巻き込まれることはないだろうが、改札内入場制限、ホーム入場制限などが行われるのだろう。乗車できてものろのろ運転、目的地までにどれだけ時間がかかるかわからない。しかも具合の悪いことに、ロンドンの地下鉄は、ホームにも電車にも冷房設備がない。といって、バスを通勤の代替手段とするのも危険極まりない。ビジネス街・繁華街を含む町の中心地は広範な交通規制の実施が予定されており、迂回と渋滞の繰り返しで地下鉄以上に時間がかかる可能性が高いからだ。そこでロンドン交通局はウェブサイトで徒歩、自転車の使用を勧めているのだが、過半の人にとってそれは有益なアドバイスとは言えない。
混乱を回避する一番の方法は、当たり前だが家から出ないことだ。実際、開催期間中の自宅勤務を認めて(勧めて)いる企業も少なくないと聞く。そうでなければ混雑が始まる前に職場に着き、混雑が終わってから帰宅する、あるいは競技真っ盛りの昼間を通勤に当てるしかない。この様な事情はロンドン居住者に不便を強いるだけではない。五輪開催に伴う経済効果を減殺させることにもなる。いわば居住者の消費需要が観光客にクラウドアウトされてしまうのだ。スリなどの犯罪増加が予想されていることも手伝って、帰宅途中や週末に町に繰り出すロンドン居住者は激減するに違いないからだ。
ロンドンは基本的な物的インフラが整備された先進国の首都である。しかし交通インフラなどの余剰キャパシティはもともと乏しい。といって、一時的な需給逼迫を避けるために大々的なキャパシティの拡張が行われることはない。それはそれで恐らく正しい。すぐ空になる箱を作ってはいけない。ただ、開催が近づくにつれ、予想される困難やコストが明確な形を取ってくる一方で、ロンドン居住者や英国が享受し得るメリットがはっきりしないままでいることに、若干の困惑を禁じ得ない。一体なぜ、この町は、五輪を招致したのだろうか?
周知のように、東京都が2020年五輪招致に立候補している。そのオフィシャル・ウェブサイトによれば、開催動機のひとつとして1964年東京五輪の成功が挙げられている。だが当時の東京と今の東京はまるで違う。60年代半ばといえば、日本が高度成長路線をまい進していた時期に当たる。当時の日本は有望新興国だったのだ。高度成長下では需要の拡大が供給サイドの各所にボトルネックを発生させ、その解消自体がビジネスになると同時に次の需要拡大の基盤になる。五輪開催に伴う交通インフラ等の拡張は供給サイド整備のスケジュールを変えるにとどまり、五輪後に箱が空になってしまうことはない。当たり前だがこれと同じ効果が2020年の東京で起こることはない。招致関係者はこれに代わる見えやすいメリットを東京都民・居住者に提示していく作業を怠るべきではないだろう。
2016年五輪はブラジルのリオデジャネイロ開催が決まっている。サッカーワールドカップは2010年大会から2022年大会まで、4回連続して新興国での開催である(南ア、ブラジル、ロシア、カタール)。国際イベントの誘致には、数多の裏話がつき物だが、それは別として、新興国開催の常態化は経済合理性に則ったものでもあり、総じてこの傾向は今後も続いていくだろう。続いていくべきなのだ。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。