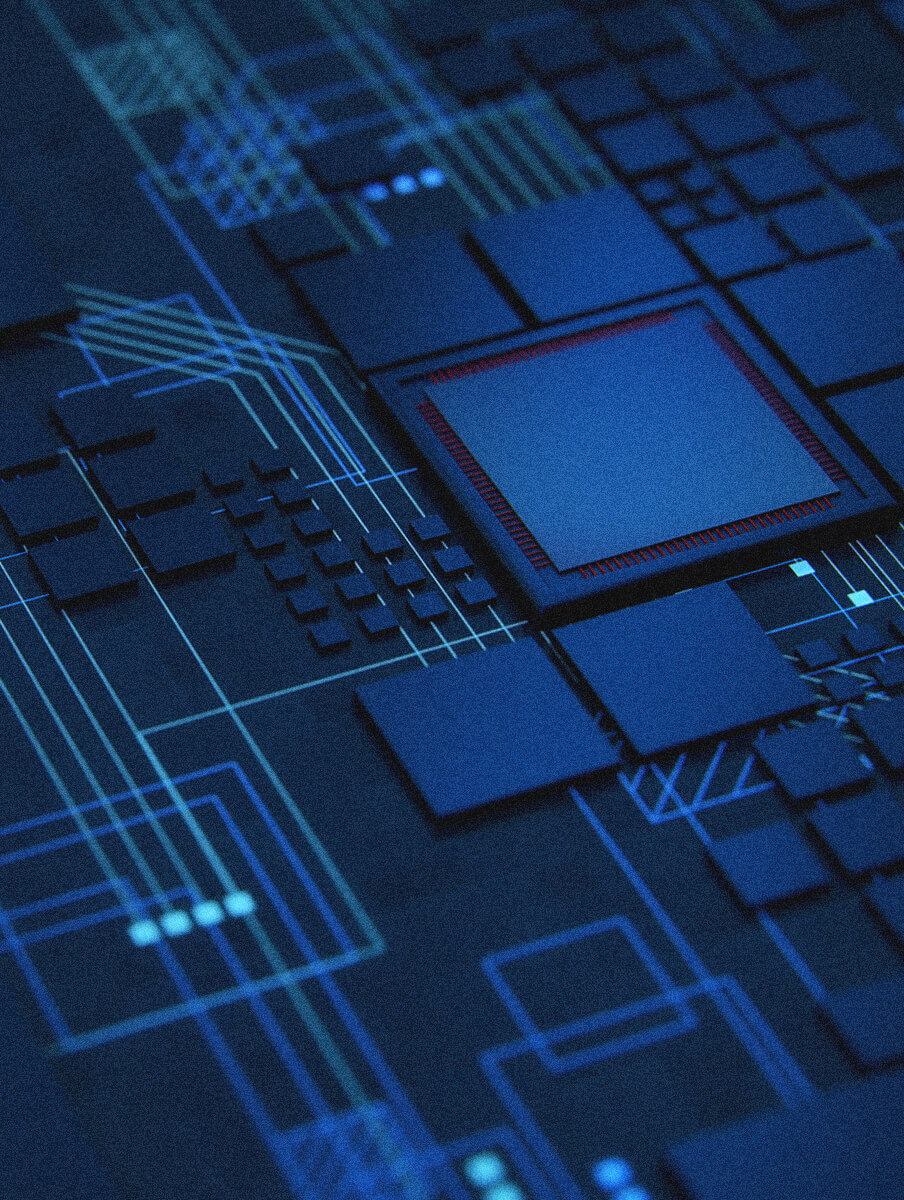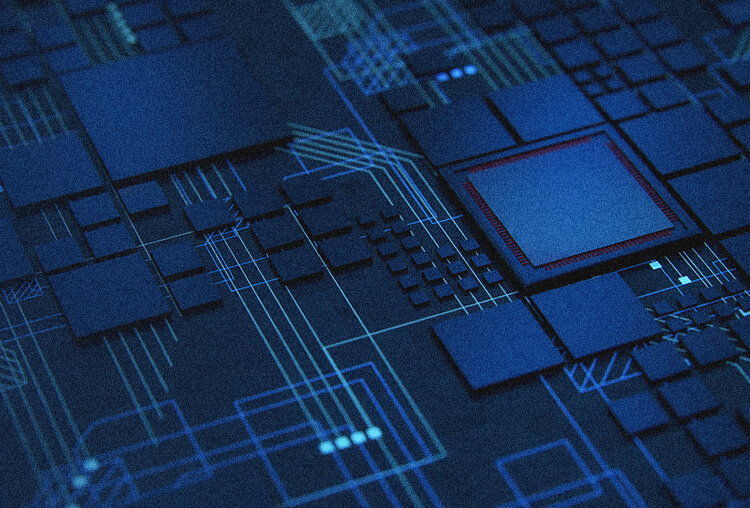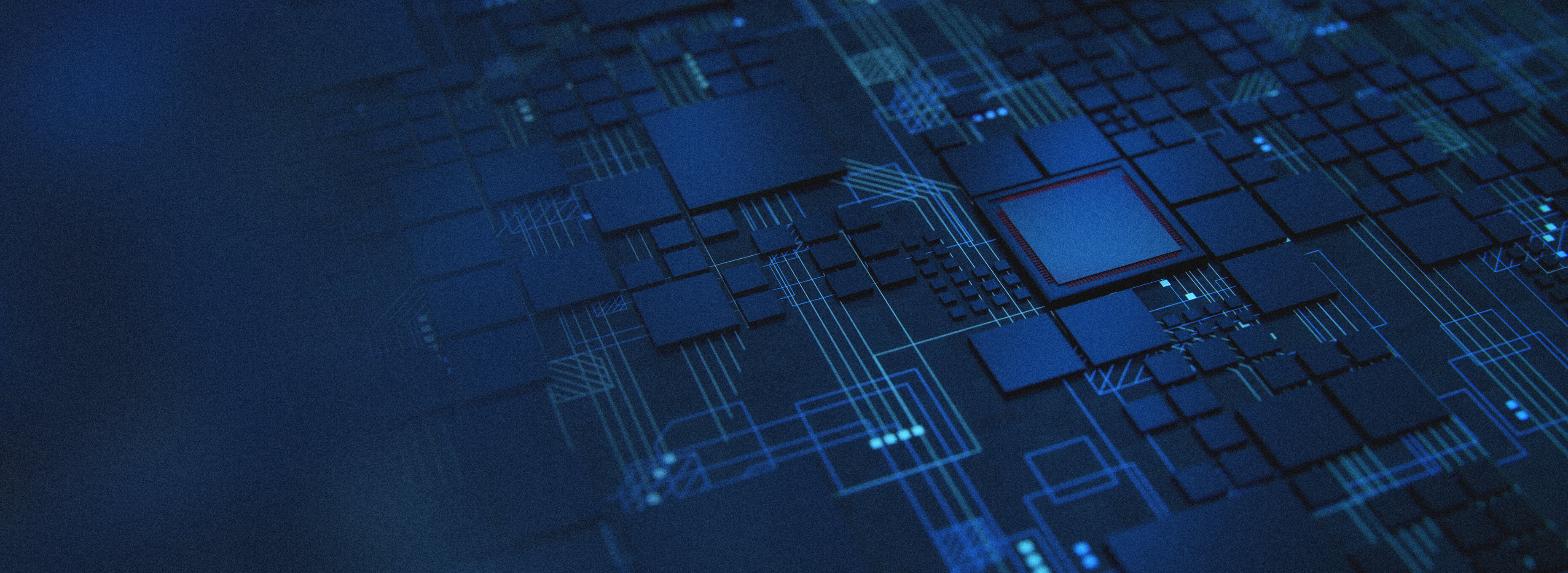「ロンドン報告 2012年春」 あなたはブリティッシュですか? イングリッシュですか?
2012年04月19日
YouGov-Cambridgeという調査機関の世論調査報告レポート(Public Opinion & the Future of Europe、発表は2012年3月15日)によれば、「あなたは自分を何人とみなしていますか」という問いに対し、英国人の60%がEnglish、7%がScottish、3%がWelsh、1%がIrishと答えており、自らをBritishとみなしている英国人は23%に留まっている。国民国家とそこに所属する国民のアイデンティティとの関係について再考を迫らずにはいない内容である。
2010年の人口統計によれば、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの人口比率は、84:8:5:3である。従ってどうやら、スコットランドとウェールズについては、ほとんどの人が自分をScottish、Welshとみなしている。Britishという回答の多くは、イングランド居住者によるということになりそうだ。
英国が現在の名称(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)となったのは1927年のことに過ぎないが、ウェールズ併合が1536年、スコットランド合併法の成立が1707年だから、両地域は数世紀にわたって統合体のもとで地域のアイデンティティを保持していることになる。時間軸にのみ注目すれば、現在の日本人が自らを薩摩人、会津人と呼び、日本人と呼ばれるのを嫌うよりも凄いことである。あるいは日本の中世、近世が、本州、九州、四国、北海道の4大王国に支配されており、国家の統一が本州の征服によって行われたものであれば、現在の英国同様、たとえば九州の人は日本人である前に九州人というアイデンティティを維持することになったのであろうか。
歴史的経緯の複雑さなどを踏まえれば、現在の英国を国民国家形成の失敗例などと評することは安易に過ぎようが、いずれにせよ、この調査結果は、人々のアイデンティティを変えることの難しさをはっきり示している。
さて、この調査によれば、自分をEuropeanと認識している英国人は2%に過ぎない。ほとんどの英国人にとっては、EnglishかBritishかを自問することはあり得ても、そこの選択肢にEuropeanが入り込む余地は残されていないのだろう。ただし、スコットランドやウェールズの多くの人にとっては、Britishと呼ばれるよりはEuropeanと呼ばれるほうがましであるかもしれない。一方で、自らをBritishと認識する23%の英国人はEuropeanと呼ばれることへの反発はより大きなものであるに違いない。この23%という数値は、国民国家の一員としてのアイデンティティの浸透を示す数値としては小さいが、EUの統合深化に英国が巻き込まれることに対する抵抗勢力としてみれば、きわめて大きな数字である。
このような人々の意識の上に、英国は現在、内にはスコットランド独立問題、対外的にはEUの中での立ち位置の再調整という現実的な問題に直面している。スコットランドにはEUというより大きな傘の存在が、UK離脱の誘因、というか一種の安心感を与えている。一方、EUは「新財政協定」が象徴するように、ユーロ圏危機の深刻化を契機として、統合の深化に舵を切ってきている。そうした中、Europeanという自覚が希薄なBritish、そして恐らくは多くのEnglishにとって、EUの統合深化が進めば進むほど、ナショナリズムが刺激され、反EU的意識が強まるというのは十分にありそうな筋書きである。
それは将来の同様の調査で、Britishと答える人の比率を引き上げることにもなるのだろう。
スコットランドは2014年に英国からの独立を問う国民投票を行う方針を掲げている。同様に、遠くない将来、英国でEUからの離脱か残留かを問う国民投票が行われるのもありえない話ではない。その際には、かなりの確率で離脱賛成票が過半に達すると考えられるが、いうまでもなく、そのような国民の声を尊重することが国益に資するとは限らない。さしあたっては、国民投票の実施を断固として回避することが、国益に即した現実的な政治のリーダシップのあり方であるかもしれない。しかし、いつ止むとも知れないユーロ圏の危機は、折に触れて「EU統合深化に対する英国の態度」を問わずにはいないだろう。当然ではあるが、ここ英国でも政治がポピュリズムに流れる危険は常にある。
翻って考えれば、こうした英国の現実は、EUが統合深化を進めるに当たり、ナショナリズムの相克を乗り越え、Europeanというアイデンティティを育んでいくことの難しさ、そしてそうしたアイデンティティを伴わない統合深化の危うさを暗示してもいる。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。