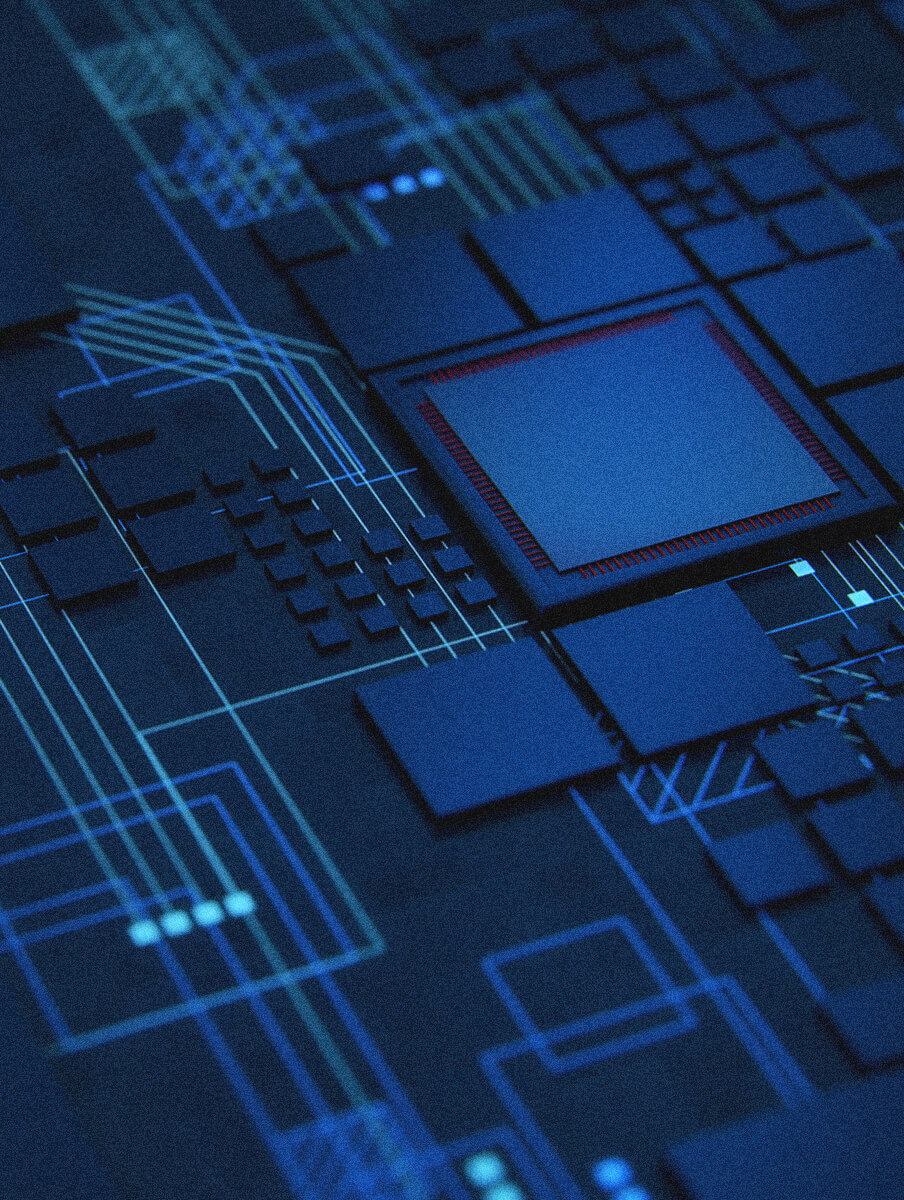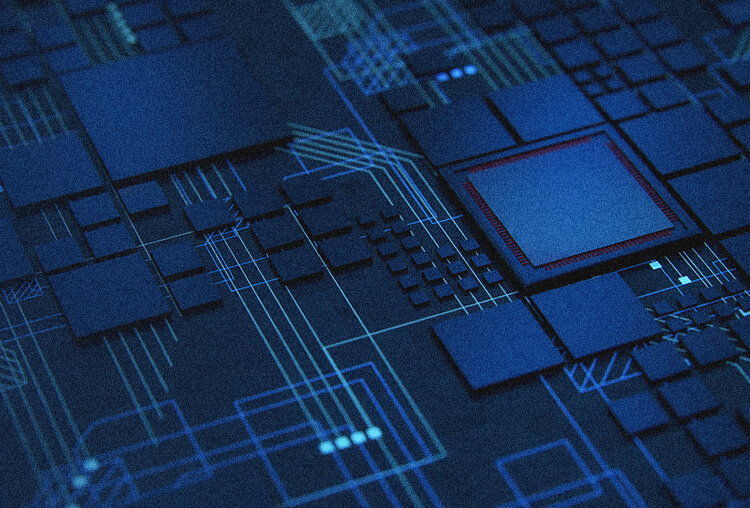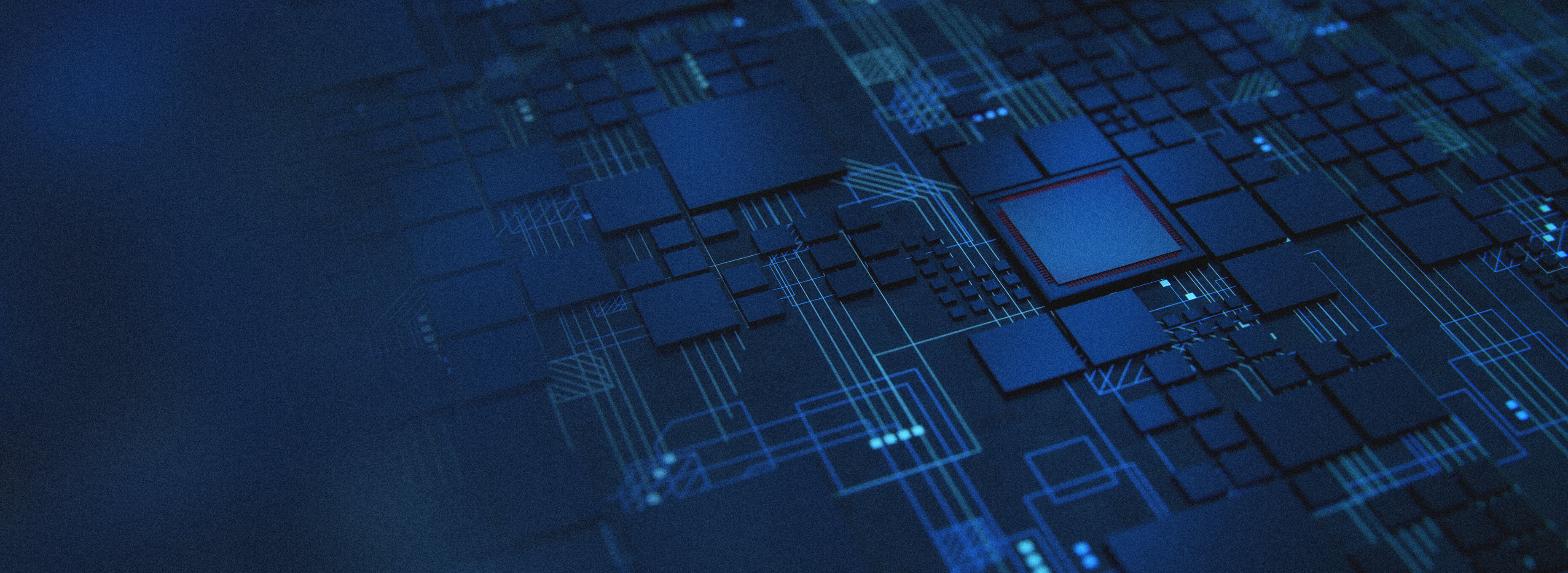会社の主は会社によって違いうる
2010年09月22日
会社の持ち主は誰か、と尋ねたら中学生でも「株主」と答えるだろう。法律上はまさにこれが正解だし、最近のガバナンス論における通説も、会社の統治は会社の所有者であり主権者である株主の権利が守られるものでなければならない、とする。
会社価値の向上はまずもって会社主権者たる株主のため、したがって株価を上げ配当金を増やすような経営をしなければならない、社長以下の経営陣は株主たちから良好な経営を行うように委任された立場に過ぎない、というわけである。こうした見解は、この2,30年間の市場経済主義の下では常識になっており、とりわけアメリカの投資家にしてみれば聞くのも愚問、のようである。この夏の金融規制改革法にはさらに一段と株主主権主義を明確にした規定が盛り込まれている。
しかし、法律論とは別に経営学の立場からはかなりの異論が出されている。
まず、最近の経営学では、株主を会社の主人公と位置づける考え方を会社用具観と称している。会社は株主が所有する用具なのであるから、煮て食べるも焼いて食べるも株主の意思次第、ということになる。良い経営とは、株主利益の極大化に他ならない。アメリカにおける通説といってよいだろう。
これに対して、伝統的なドイツなど欧州の認識や日本の企業社会で根強い考え方を、多元的用具観あるいは会社制度観と呼んでいる。多元的用具観とは、会社は株主の用具であるのみならず、従業員、取引先、経営者等々の多元的なステークホルダーの用具でもあるとみなすもの、会社制度観とは会社はその存在自体に社会的意義を持っており、特定のステークホルダーの用具ではない、と考えるもの、である。
実はよくよく考えてみると、いずれの会社観によっても最終的な結論に大差はない。いずれも資本と労働が協業しながら社会に果実をもたらし、こうした一連の付加価値創造活動に寄与したものに相応のリターンを均霑させる有機的組織を会社と位置づけているのだ。
もっとも証券市場が発達する中で、法制度上のガバナンスや権利義務関係、責任の所在を明確にするためには、株主用具論が一番やりやすいのだろう。
だが、ここで少し考えたいのは、東京証券取引所1部上場の多数の従業員を抱え歴史も長い大企業と新興市場に上場したばかりの企業を同列に扱ってよいか、という点だ。
日本企業の長期安定的な発展を期しつつ将来性の高い成長エンジンを起動させるためには、1部上場大企業には会社制度観を当てはめ、新興企業には会社用具観を適用していくのが現実的で有効なのではないか、と思う。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
関連のレポート・コラム
最新のレポート・コラム
-
生成AIが描く日本の職業の明暗とその対応策
~AIと職業情報を活用した独自のビッグデータ分析~『大和総研調査季報』2024年春季号(Vol.54)掲載
2024年04月25日
-
大手生保は中長期の事業環境の変化に対応できるか
~本格化するビジネスモデル変革~『大和総研調査季報』2024年春季号(Vol.54)掲載
2024年04月25日
-
企業価値向上に向けて上場会社に高まるプレッシャー
『大和総研調査季報』2024年春季号(Vol.54)掲載
2024年04月25日
-
長期デフレからの本当の出口
『大和総研調査季報』2024年春季号(Vol.54)掲載
2024年04月25日
-
複眼的思考へのヒント
2024年04月24日